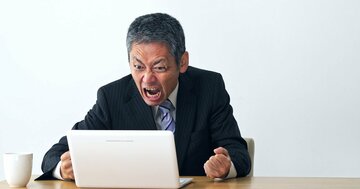岩本 しかしながら、今回のドイツについては、人口比で言うならば日本の人口(2021年、1億2570万人)はドイツの人口(2021年、8320万人)のおよそ1.5倍となります。そのドイツに日本が追い抜かれてしまうわけですから、「ショック」を受ける気持ちもわからなくもありません。
生島 かつての日本経済が世界をブイブイ言わせている時代を知っている身としては、ちょっと寂しい限りですね。
なぜ実質GDPではなく名目GDPを選んだのか
岩本 先ほど報道での取り上げ方に関して、違和感があったと申し上げました。というのも報道で取り上げられていたのがIMFの最新予測の中でも「実質GDP」ではなく、「名目GDP」だったためです。
生島 何か裏があるというか、別の目的があるのではないか、と。
岩本 シンプルに日本がダメだ、危ないというほうがニュースとしてセンセーショナルで人目を引きやすい、というのがあるのかもしれません。あるいは日本はダメとしたほうが、海外への投資などを促せる、そうした商品を販売している人たちにとっては都合がよいのかもしれません。
ここで名目と実質の違いですが、名目GDPというのは物価変動の影響を踏まえた数値です。それに対して物価変動の影響を取り除いたものが実質GDPとなります。
例えば名目GDPがこれまでと比べて、ある時点で2倍になったとします。たしかに数字としては2倍になったとしても、そのまま国の経済規模が2倍になったかどうかは名目GDPではわかりません。というのも名目GDPは、モノの値段が上がれば、たとえ経済規模が大きくなっていなくても数字が大きくなってしまうからです。そこで、物価変動の要素を取り除いた実質GDPを見ることで、実際に経済規模がどれくらい成長しているのかを把握するわけです。
2023年のドイツの消費者物価上昇率は6%、かたや日本は3%でした。そのため名目GDPであれば物価上昇率が高いドイツの数字は嵩(かさ)増しされます。
そしてIMFの報告書は米ドルベースとなります。日本のGDPが同じ633兆円であっても、円安時は633兆円÷149円=4.2兆ドルとなり、ドル換算では目減りしてしまいます。対して、例えばコロナ感染症が確認されWHOがパンデミック宣言した2020年3月のドルの最安値101円で計算すると、633兆円÷101=6.2兆ドルと嵩増しされる、という具合です。つまり、名目GDPでは物価と為替変動の影響があって、実際の経済状況の正確な把握がしにくいんです。