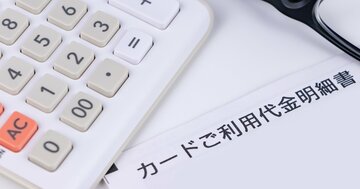在職時より1万円以上アップの可能性も
退職直後の保険料に注意
国民健康保険料は、前年(1月1日~12月31日まで)の所得によって決められている。例えば、定年退職すると主な収入は公的年金だけになり、現役世代に比べて所得は低くなる。だが、保険料は退職前の高い年収をもとに計算されるため、退職直後は実際の支払い能力以上の高い保険料になることがある。
一方、任意継続被保険者の保険料は、在職中の標準報酬月額をもとに計算する。在職中は労使折半で事業主負担があったが、任意継続被保険者は全額自己負担になる。例えば、東京都の協会けんぽに加入している人(40歳未満)で、退職時の標準報酬月額25万円だった場合、在職時は1万2974円だった保険料が、退職後は2万5948円になる(2024年度)。
ただし、これまで、任意継続被保険者の保険料は、最大でも「加入者全体の標準報酬月額の平均」をもとに計算するというルールが設けられていた。そのため、退職時の月収が高くても保険料は一定の範囲に抑えられ、事業主負担がなくなっても、国民健康保険に比べて保険料が安くなる人が多かったのだ。
ところが、2022年に法改正が行われ、現在はそれぞれの健保組合の判断で、「退職時の標準報酬月額未満の範囲内の金額」まで保険料が引き上げることが可能になっている。
今のところ保険料の引き上げには慎重な組合も多く、協会けんぽでは従来通りの計算方法を採用しているので、任意継続被保険者の保険料は最大でも標準報酬月額30万円を基準としたものとなっている。
だが、健保組合の中には、退職前の標準報酬月額をもとに任意継続被保険者の保険料を徴収しているところもある。
例えば、保険料率10%の健保組合で、退職時の標準報酬月額が60万円、加入者全体の標準報酬月額が30万円だった場合で、以前なら任意継続被保険者の保険料は最大でもげ3万円だった。ところが、現在は6万円の負担を求める健保組合も出てきているのだ。
一概に、任意継続被保険者が有利になるといは言えなくなっているので、少しでも保険料負担を抑えたい場合は、国民健康保険の保険料と比較して安い方を選ぶようにしよう。