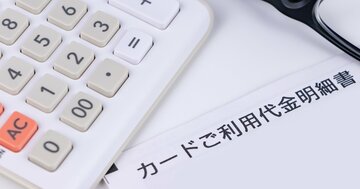被扶養者は保険料負担なし!
真っ先に検討したい選択肢
会社員が加入する健康保険は、主に中小企業の従業員を対象とした全国組織である「全国健康保険協会(協会けんぽ)」、ひとつの企業、または同業種の企業が集まって独自に運営する「組合管掌健康保険(組合健保)」のいずれかで、入社すると勤務先が加入手続きをしてくれる。
被保険者(加入者)には被保険者証が配られ(マイナ保険証で対応しているケースもある)、これを見せれば、全国どこの医療機関でも一部負担金を支払うだけで必要な医療を受けられる。
ところが、退職すると健康保険も資格喪失手続きが取られ、被保険者証も返還しなければならない。退職日の翌日から、それまでの健康保険は使えなくなるので、すみやかにその他の健康保険への加入手続きをとる必要がある。
退職が決まった後、年次有給休暇を消化して、間を空けずに退職日の翌日に再就職する場合は、次の会社で新しい健康保険の加入手続きをしてくれる。だが、すぐに再就職しない場合は、次の3つの中から加入先を選ぶことになる。
(1)被用者保険に加入している家族の被扶養者になる
(2)退職した会社の健康保険の任意継続被保険者になる
(3)国民健康保険に加入する
ただし、誰でも自由に加入先を選べるわけではなく、それぞれに加入要件がある。メリット・デメリットも異なるので、詳しく見てみよう。
(1)被用者保険に加入している家族の被扶養者になる
退職後の健康保険で、最初に検討したいのが「被扶養者」という選択肢だ。夫や妻、親、子どもなどの家族が会社員や団体職員などで、被用者保険に加入していれば利用できる可能性がある。
被扶養者は、被保険者(加入者)に扶養されている親族のための制度で、次の要件を満たしている場合に、協会けんぽや組合健保など労働者のための健康保険(被用者保険)に保険料の負担なしで加入できることになっている。
・75歳未満であること
・被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹で、生計維持関係にあること(必ずしも同居の必要はない)
・同居していて生計維持関係にある三親等以内の親族(事実婚も可能)
・年収130万円未満(60~74歳は180万円未満)。同居の場合は、原則的に被保険者の収入の1/2未満。同居していない場合は、被保険者からの仕送り等の援助金を超えていないこと
健康保険料は、被保険者の所得に一定の保険料率をかけて決められる。被扶養者が何人いても金額は変わらない。例えば、結婚退職した妻が、夫の健康保険に加入しても、夫の保険料負担が増えることはなく、妻は保険料の負担なしで健康保険に加入できる。当面の保険料を抑えられるので、上記の要件を満たしている場合は、真っ先に検討したい制度だ。