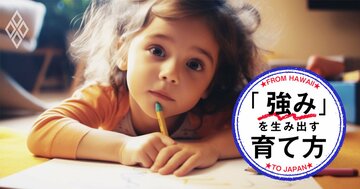学校も社会も「教える人が偉い」
伊藤:坪田さんがおっしゃったのは、マスの教育、1対50だとなかなか伸びない。それを「子別」指導にしていくのは革命だったけど、それでも限界がある。そこからの、「ITやAIを使って」という2段階だと思うんです。
その1段階目、一人ひとりに目を向けるところについて、「坪田さんは気づかれました」「〇〇さんは気づかれました」となってきています。
坪田:そうですね。
伊藤:だけど、そこがいまだに、「そうは言っても無理じゃん」「手間がかかりすぎじゃん」となっている。
塾だと、「それでもやるんだ」と言って変えることができるけど、学校教育においては「教えて育てる」「指示して導く」といった、完全に教師側に立ったマスの部分がなくなっていないと思うんですよ。
坪田:おっしゃるとおりです。
伊藤:一方で、「でも、どう考えても一人ひとりだよね」と、みんなわかり始めているわけですね。
坪田:はい(笑)。
伊藤:坪田さんは、「手間がかかりますよね」「お金がかかりますよね」ということに関して、どんなふうにおっしゃっているんですか?
尾原:めっちゃ興味があります。
坪田:めっちゃおもしろい(笑)。教育の対談で、ここまで「そうですよね」と思うことはなかなかないので、すごくうれしいです。
「手間がかかりますよね」「お金がかかりますよね」に対する回答でいろいろ言っているんですが、つまり、「短期的に手間暇」がかかるし「お金がかかる」子別の対応って、100人が100人伸びるので、長期的にはコストが低いと考えています。
1人を伸ばすために99人から搾取する構造は、シンプルにコストが高すぎると思うんです。
ただ、おっしゃるとおり、「とはいえ」というのがあります。これ、実は学校教育だけじゃなくて、おそらく社員教育でも同じなんですよね。ほとんどのケースで、上司は自分の成功体験があるし、「自分はこう学んできた」というのがあるので、新人を指導する時に「俺のやり方」をするんですよ。
当然、合う・合わないが出てきます。めちゃくちゃ合う部下は「右腕」のようになって、それを成功体験として「他のやつらはついてこれなかった」となりがちです。なので本質的には、学校教育も社会に出てからも、同じ教育スタイルです。やっぱり、「教える人が偉い」じゃないですか。
尾原:そうですね。
坪田:社会人になるとなおさらです。
尾原:「上司」ってなっちゃうからですね。
坪田:経験値も高いし、社会に対する影響もデカいでしょうから、「上司」となるのが当然な部分はあります。