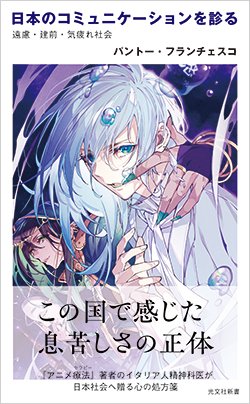 『日本のコミュニケーションを診る~遠慮・建前・気疲れ社会』(光文社)
『日本のコミュニケーションを診る~遠慮・建前・気疲れ社会』(光文社)パントー・フランチェスコ 著
海外においても、我慢は日本で美化されやすいものとして知られている。また、ハリウッド映画では主人公が悪人を倒して愛を見つける物語が典型的であるが、日本の物語は幸せな結末より、主人公の痛みと苦しみに焦点を当てる傾向があることが研究者たちに指摘されている。
我慢は日本の子どもたちに早い段階で教えられる。臨床心理学者の小田切紀子は、我慢と忍耐は日本の教育の一部であり、その尊さは小学校から学習されると指摘する。特に女性に対しては、可能な限り我慢を教育する。小田切は、過剰な我慢はメンタルヘルスに悪影響を及ぼす懸念があり、自分の気持ちに対する否定感を持ちすぎると我慢は心身症に変わるのではないかと述べている。また、怒りが爆発して家庭内または職場での暴力につながる可能性があることも示唆されている。
筆者の解釈でも「辛抱」と「我慢」は違う。前者は一時的に自分の快楽や欲求を抑え、先延ばしにすることだが、後者は集団から排除されないために、無期限に自分の欲求を押し殺すことに近い。適応できていない職場で、理不尽なお客さんにも礼儀正しく対応する。いじめられても、何事もなかったように笑顔を取りつくろう。自分の意見を述べて相手と対立するより、過半数に無理やり賛同する。こうした我慢のエピソードは巷にあふれているだろう。
だからといって、我慢が全て悪いわけでもない。犯罪学を専門とする小宮信夫は、我慢は社会と個人に対して利益があると述べる。己の欲望を抑える日本の国民は自制心が強く、国民間の相互監視とあわせて日本の犯罪率が世界有数に低いことの一因であると考えられる。







