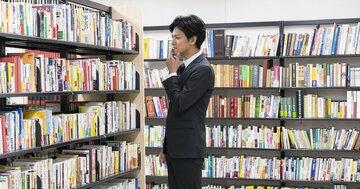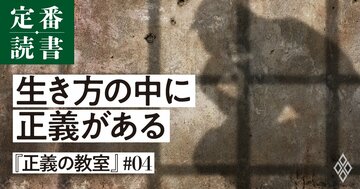他方、アニメ表現を擁護する側にも別種の被害者意識がみられます。アニメの制作者や愛好者は誰にも迷惑をかけることなく、その表現を楽しんできた。ところが、根拠も乏しいままに自分たちが育んできた表現を「差別」として糾弾し、規制しようとする人びとが存在しており、このままでは表現の幅がどんどん狭められてしまう。この観点からすれば、(私を含め)自由な表現を封じ込めようとする人びとこそが加害者であり、アニメや漫画の制作者やファンはその被害者ということになります。
お互いの関係性が被害者/加害者として認識される場合、両者の対話が建設的になる可能性は限りなく低くなります。しかし、ソーシャルメディア上での論争はまさにそうした形態をとるがゆえに、妥協の余地が全く生じなくなってしまうのです。
「被害者でありたい」心理の背後にある
「力」をもつ者への不信感
それではなぜ、自らを被害者として位置づけようとする動きが顕著になっているのでしょうか。それを考えるためのヒントになるのが、今から半世紀前に庄司薫という小説家が出版した『狼なんかこわくない』というエッセイです。以下では、ソーシャルメディアの問題を少し離れ、この作品を出発点として被害者になろうとする心理について考えてみることにしましょう。
庄司によれば、若者自身の手によるものも含め、青春について論じた著作の多くが「若者=傷つきやすく、か弱い存在」だという前提に立っているといいます。しかし、自らの幼年期を振り返ってみると、その等式は全く成立しないとして、庄司は次のように論じます。
幼稚園や小学校においてすら、教室は権謀術数(人を欺くたくらみ)の渦巻く場だった。たとえ成長途上の若者であっても、人に危害を加える力をもっている。しかも、そうした力は「自分は他人からなされるがままの無力な存在ではない」というプライドの源泉にもなりうる。ところが、若者はそういったプライドを簡単に投げ捨て、とにかく無力な被害者としての立場に自らを置こうとする。
「被害者でありたい」というそのような心理の背後には、「傷つきやすさ・弱さ=純粋さ・誠実さ」という発想や、「力」をもつ者に対する強い不信感がある。つまり、「弱いやつこそ人間らしくよいやつで、強いやつほど悪いやつ」だということだ。権力者がしばしば非人間的で不誠実な加害者だとみなされるのも、こうした発想の反映である。