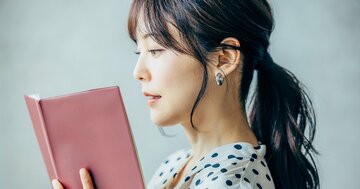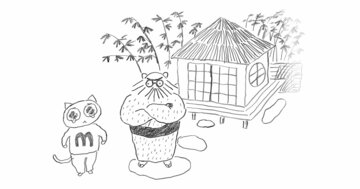写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
学生時代は本を読むのが日常だった“読書好き”も、社会に出て働くうちに本から遠ざかってしまった――。そんな悩みを持つビジネスパーソンは少なくない。文芸評論家の三宅香帆氏は、大ヒット映画『花束みたいな恋をした』には労働と読書を両立する難しさが描かれている、と分析する。“本をじっくり読みたすぎるあまり、会社をやめた”著者が、現代の読書人が抱えるジレンマをひもとく。※本稿は、三宅香帆『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社)の一部を抜粋・編集したものです。
大ヒット映画で描かれた
労働と読書の“リアル”
絹「……」
麦「ゴールデンカムイだって七巻で止まったまんまだよ。宝石の国の話もおぼえてないし、いまだに読んでる絹ちゃんが羨ましいもん」
絹「読めばいいじゃん、息抜きぐらいすればいいじゃん」
麦「息抜きにならないんだよ、頭入んないんだよ。(スマホを示し)パズドラしかやる気しないの」
絹「……」
麦「でもさ、それは生活するためのことだからね。全然大変じゃないよ。(苦笑しながら)好きなこと活かせるとか、そういうのは人生舐めてるって考えちゃう」
(坂元裕二『花束みたいな恋をした』)
生活するためには、好きなものを読んで何かを感じることを、手放さなくてはいけない。そんなテーマを通して若いカップルの恋愛模様を描いた映画『花束みたいな恋をした』は、2021年(令和3年)に公開され、若者を中心にヒットした。私自身は主人公の年齢とほぼ同い年なのだが、面白く観たし、なにより働いている同年代の友人たちが「最近観た映画のなかで一番身につまされたよ……」となんとも言えない表情で感想を語っていたのが印象的だった。実際、ネットでもずいぶん熱心な感想を書く人は多かった。
この映画の主人公は、麦と絹という一組のカップルである。大学生のときに出会い、小説や漫画やゲームといった文化的趣味が合ったふたりは、すぐに恋人になる。しかし同棲し就職するなかでふたりの心の距離は離れていく。とくに会社の仕事が忙しくなった麦は、それまで好きだった本や漫画を読まなくなる。そんな麦に、絹は失望を抱えるようになる。
『花束みたいな恋をした』において、長時間労働と文化的趣味は相容れないものとされる。麦は営業マンとして夜遅くまで働く一方、絹は残業の少ない職場で自分の趣味を楽しんでいる。ふたりのすれちがいが決定的になるのは、絹が出張に行く麦に、芥川賞作家の滝口悠生の小説『茄子の輝き』を手渡すシーン。麦はそっけなく受け取り、出張先でも本を乱暴に扱うさまが映し出される。
一見よくある若いカップルの心の距離を描いた物語だが、このストーリーの背後には、「労働と、読書は両立しない」という暗黙の前提が敷かれている。