三宅香帆
TikTokでショート動画を見続けた人の「脳」に起こること
SNSが多くの人の心をつかむ理由は、いいねやフォロワーで「報われたい」欲を満たす設計を巧みに採り入れているからだ。しかし、TikTokはその前提を満たさないにもかかわらず、若い世代を虜にしている。ユーザーの時間を溶かすように奪う、新しくも恐ろしい仕組みとは。※本稿は、文芸評論家の三宅香帆『考察する若者たち』(PHP研究所)の一部を抜粋・編集したものです。

三宅香帆が指摘する「ひろゆき」と「ホリエモン」の本質的な違い
ひろゆきが人気だ。SNSでもテレビでも彼を見ない日はないが、そのフォロワーを見てみると弱者が多い印象を受ける。なぜひろゆきの言葉は、生きづらさを抱えた人に響くのか。論破王が令和に受け入れられた背景に迫る。※本稿は、文芸評論家の三宅香帆『考察する若者たち』(PHP研究所)の一部を抜粋・編集したものです。

三宅香帆が教える「異世界転生もの」と「ループもの」の決定的な違い
異世界転生ものが空前のブームだ。『転生したらスライムだった件』をはじめ、『幼女戦記』『【推しの子】』など、多くの作品が爆発的な人気を獲得し、もはやジャンルとして完全に定着した。しかし、これらの作品がヒットする原因を探っていくと、現代社会特有の残酷な価値観に支えられていることがわかってきた。『転スラ』ブームに潜む社会の病理とは?※本稿は、文芸評論家の三宅香帆『考察する若者たち』(PHP研究所)の一部を抜粋・編集したものです。

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』の著者が「もともと動物にまったく興味のない私ですら“えー! そうなんだ!”とうなずいているうちに、気が付いたら読み終えていた」と語る“分厚い本”とは?〈再配信〉
発売たちまち重版続々のベストセラー!! ウォール・ストリート・ジャーナル、ガーディアン、サンデータイムズ、各紙絶賛! 生き物たちは、驚くほど人間に似ている。ネズミは水に濡れた仲間を助けるために出かけるし、アリは女王のためには自爆をいとわない。カケスは雛を育てるために集団で保育園を運営し、ゾウは亡くなった家族の死を悼む。あまりよくない面でいえば、バッタは危機的な飢餓状況になると仲間に襲いかかり、動物園の器具を壊したゴリラは怒られるのが嫌で犯人は同居している猫だと示す…といったように、どこか私たちの姿をみているようだ。シドニー大学の「動物行動学」の教授でアフリカから南極まで世界中を旅する著者が、好奇心旺盛な視点とユーモアで、動物たちのさまざまな生態とその背景にある「社会性」に迫りながら、彼らの知られざる行動、自然の偉大な驚異の数々を紹介。「オキアミからチンパンジーまで動物たちの多彩で不思議な社会から人間社会の本質を照射する。はっとする発見が随所にある」山極壽一(霊長類学者・人類学者)、「アリ、ミツバチ、ゴキブリ(!)から鳥、哺乳類まで、生き物の社会性が活き活きと語られてめちゃくちゃ面白い。……が、人間社会も同じだと気づいてちょっと怖くなる」橘玲(作家)と絶賛されたその内容の一部を紹介します。
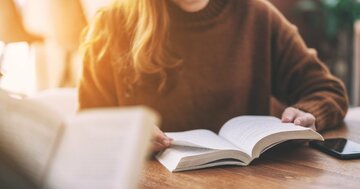
「好きなことを仕事にしたい」→ベストセラー作家のアドバイスが的確すぎて「確かに」しか言えない…
「書店員が選ぶノンフィクション大賞2024」に輝き、販売数20万部を超えた文芸評論家・三宅香帆さんの『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社新書)。ビジネスパーソンに刺さるタイトルをはじめ、「歴史上、日本人はどうやって働きながら本を読んできたのか?なぜ現代の私たちは、働きながら本を読むことに困難を感じているのか?」を丹念にひも解いた内容が多くの人を魅了している。そんなヒット作を生み出した三宅さんに、「好き」を仕事にする方法を聞いた。

【メモの取り方】なぜ、頭のいい人は具体例がすぐに出てくるのか……?
「メモを取りましょう」多くの人が言われたことのある言葉だ。2023年と2024年のビジネス書年間ランキングで2年連続1位を獲得した『頭のいい人が話す前に考えていること』の著者でコンサルタントの安達裕哉氏と、今話題の新書『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社新書)と『「好き」を言語化する技術』(ディスカヴァー携書)の著者であり文芸評論家である三宅香帆氏が、メモの取り方について語り合った。コンサルタントと文芸評論家のいう、「頭のいい人たち」のメモの取り方とはどのようなものだろうか。(文/神代裕子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)

【コンサルと書評家が教える】「仕事をするすべての人に読んでほしい本」と「サラッと読めるけど日常が違って見える本」
「書店員が選ぶノンフィクション大賞2024」を受賞した『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社新書)の著者で文芸評論家・三宅香帆氏。そして、2023年と2024年のビジネス書年間ランキング2年連続1位を獲得した『頭のいい人が話す前に考えていること』の著者でコンサルタントの安達裕哉氏。現在話題の本の著者である二人は、どちらも読書が大好きという。動画が台頭する現代においても読書を楽しんでいる二人がオススメする本を聞いた。(文/神代裕子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)
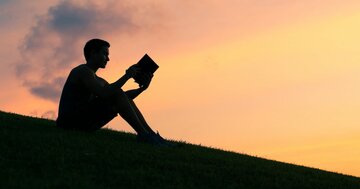
【プレゼン資料の1枚目】仕事のできる人は「自己紹介」ではなく、何を書く……?
「人が本を読まなくなる理由」を労働の側面から紐解いた新書『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社新書)が、ベストセラーとなり話題となっている。著者は文芸評論家である三宅香帆氏だ。2023年と2024年、2年連続でビジネス書ランキング1位を獲得した『頭のいい人が話す前に考えていること』の著者でコンサルタントの安達裕哉氏が、三宅氏に文芸評論家の仕事について話を聞いた。文芸評論家とコンサルタントとの意外な共通点に迫る。(文/神代裕子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)

「すぐに結論を求める人」の末路と「頭のいい人」が本を読むワケ【安達裕哉×三宅香帆】
文化庁による2023年度の「国語に関する世論調査」で、月に1冊も本を読まない人が6割超に上ることが判明した。このように本を読まない人が増えている中、「人が本を読まなくなる理由」を労働史の側面から紐解いた新書『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社新書)が、23万部を突破し話題となっている。その著者であり文芸評論家である三宅香帆氏に、2023年と2024年のビジネス書ランキングで2年連続1位に輝いた『頭のいい人が話す前に考えていること』の著者でコンサルタントの安達裕哉氏が話を聞いた。読書家である安達氏と三宅氏が考える「本が読めなくなる理由」と、二人が本を読み続ける理由とは何か。(文/神代裕子、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)

【コンサルから教わった】感じのいい人が忙しくてもやっているたった1つのこと
耳を傾ける、話を聞く、ということが年々難しくなっているような気がする。 そう語るのは、「書店員が選ぶノンフィクション大賞2024」を受賞した『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社新書)や『「好き」を言語化する技術』(ディスカヴァー携書)がベストセラーとなっている文芸評論家・三宅香帆氏。三宅氏は2023年と2024年のビジネス書年間ランキング2年連続1位を獲得した『頭のいい人が話す前に考えていること』を読み、コンサルが書くコミュニケーション本としては意外な点があったそう。三宅香帆氏に文芸評論家ならではの視点で本書の魅力を寄稿いただいた(ダイヤモンド社書籍編集局)。

【そりゃ売れるわ】文芸評論家が驚いた「頭がいいと思われる人」だけがやっている意外だけど本質的なこと
「書店員が選ぶノンフィクション大賞2024」を受賞した『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社新書)や『「好き」を言語化する技術』(ディスカヴァー携書)がベストセラーとなっている文芸評論家・三宅香帆氏。三宅氏は2023年と2024年のビジネス書年間ランキング2年連続1位を獲得した『頭のいい人が話す前に考えていること』を読み、「そうか、本書の語り口こそが、頭の良い人の話し方なのか!」と驚かされたそう。三宅香帆氏に本書の魅力を寄稿いただいた(ダイヤモンド社書籍編集局)。

ベストセラー『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』著者が、疲れ切った会社員に薦めたい本とは?
「書店員が選ぶノンフィクション大賞2024」に輝き、販売数20万部を超えた文芸評論家・三宅香帆さんの『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社新書)の勢いが止まらない。ビジネスパーソンに刺さるタイトルをはじめ、「歴史上、日本人はどうやって働きながら本を読んできたのか?なぜ現代の私たちは、働きながら本を読むことに困難を感じているのか?」を丹念にひも解いた内容が多くの人を魅了している。そんなヒット作を生み出した三宅さんに、同書の狙いや読書術、オススメの本などについて話を聞いた。

「推し」がスキャンダルを起こした時、ファンが投稿するべき言葉とは?
気軽に推しへの想いをSNSへ投稿できる今、大量に流れてくる言葉の渦に飲まれ、他人の発信する意見や感想に引っ張られて自分の感想がブレてしまうことも……。そんな時代において大切なのは、他人の意見と自分の意見の「違い」に自覚的になること。推しに対する自分だけの感情を見失わないコツを、書評家の三宅香帆氏が解説する。※本稿は、三宅香帆『「好き」を言語化する技術 推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない』(ディスカヴァー携書)の一部を抜粋・編集したものです。

「パクチーの美味しさ」を伝える時、真っ先に考えるべきこと
自分の好きなモノについて熱く語ったのに、相手との温度感が違ってイマイチ話が盛り上がらなかった……なんて経験はないだろうか。「好き」を言語化するプロである書評家の三宅夏帆氏曰く、伝えようとする情報に対する相手のスタンスを知ることが、相手を聞く気にさせるための第一歩なのだとか。昨年出版と同時にSNSを中心に大きな話題をよんだ書籍のハンディ版『「好き」を言語化する技術 推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない』(三宅香帆 著、ディスカヴァー・トゥエンティワン)より一部抜粋・編集して、押し語りのコツをお届けしよう。
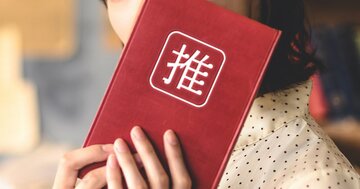
SNSにはびこる陳腐すぎる感想3パターン「泣ける」「やばい」…あと1つは?
演劇、アニメ、ドラマ、スポーツなど、さまざまなエンタメが溢れる現代では、人は誰しも感動したことを他者に語りたがる。しかし、「泣ける」「考えさせられる」といったお決まりのワードを口にした途端、せっかくの感想もありふれたものになってしまう。書評家・三宅香帆氏が語る“自分だけ”の言葉で感想を述べることの意義とは?昨年出版と同時にSNSを中心に大きな話題をよんだ書籍のハンディ版『「好き」を言語化する技術 推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない』(三宅香帆 著、ディスカヴァー・トゥエンティワン)より、一部抜粋・編集してお届けする。

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』の著者が「もともと動物にまったく興味のない私ですら“えー! そうなんだ!”とうなずいているうちに、気が付いたら読み終えていた」と語る“分厚い本”とは?
発売たちまち重版続々のベストセラー!! ウォール・ストリート・ジャーナル、ガーディアン、サンデータイムズ、各紙絶賛! 生き物たちは、驚くほど人間に似ている。ネズミは水に濡れた仲間を助けるために出かけるし、アリは女王のためには自爆をいとわない。カケスは雛を育てるために集団で保育園を運営し、ゾウは亡くなった家族の死を悼む。あまりよくない面でいえば、バッタは危機的な飢餓状況になると仲間に襲いかかり、動物園の器具を壊したゴリラは怒られるのが嫌で犯人は同居している猫だと示す…といったように、どこか私たちの姿をみているようだ。シドニー大学の「動物行動学」の教授でアフリカから南極まで世界中を旅する著者が、好奇心旺盛な視点とユーモアで、動物たちのさまざまな生態とその背景にある「社会性」に迫りながら、彼らの知られざる行動、自然の偉大な驚異の数々を紹介。「オキアミからチンパンジーまで動物たちの多彩で不思議な社会から人間社会の本質を照射する。はっとする発見が随所にある」山極壽一(霊長類学者・人類学者)、「アリ、ミツバチ、ゴキブリ(!)から鳥、哺乳類まで、生き物の社会性が活き活きと語られてめちゃくちゃ面白い。……が、人間社会も同じだと気づいてちょっと怖くなる」橘玲(作家)と絶賛されたその内容の一部を紹介します。
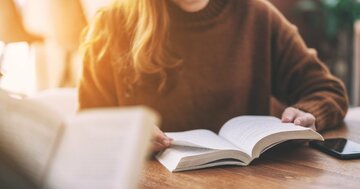
だからこそ「母殺し」が必要だ…2000年代の「VERY妻」に角田光代の小説が伝えたかったこと
母はしばしば、自身の夢やコンプレックスを娘に投影するものである。一方、母から与えられた規範の存在に気付かないまま大人になっている娘は多い。2000年代に女性誌『VERY』で連載された角田光代の小説『銀の夜』の作品読解を通じて、母の規範の再生産に巻き込まれる娘たちの課題に迫る。※本稿は、『娘が母を殺すには?』(三宅香帆、PLANETS/第二次惑星開発委員会)の一部を抜粋・編集したものです。

『ママレード・ボーイ』『こどものおもちゃ』…90年代少女漫画の「自由奔放な母親」はなぜ生まれたのか?
1990年代の少女漫画には、「理想の母」という流行があった。こうした物語において母娘の仲はよく、家庭は明るい。しかし、文芸評論家の三宅香帆は、フィクションの世界で「理想の母」が描かれることにはある危うさがあると指摘する。※本稿は、『娘が母を殺すには?』(三宅香帆、PLANETS/第二次惑星開発委員会)の一部を抜粋・編集したものです。

58歳の母親を殺害した31歳の女子大生が、それでも「母の許し」を求めたワケ
母から娘に与えられる厳しすぎる規範は呪縛となり、時に悲劇を招く。2018年には、医学部への進学を強要され、9年間もの浪人生活を強いられた娘が、母親を殺害する事件が起きた。事件の背後には、母の規範に縛られた娘の苦悩と、「母に許されたい」という強迫観念があった。母が娘の人生にどれほど強い影響を及ぼすか、どうすれば娘は母の呪縛から逃れられるのか。母と娘を題材にした作品読解を通じて考察する。※本稿は、『娘が母を殺すには?』(三宅香帆、PLANETS/第二次惑星開発委員会)の一部を抜粋・編集したものです。

今はなき雑誌「BIG tomorrow」は、なぜビジネスパーソンにあれほど刺さったのか?
1980年代、出版業界の売り上げはピークを迎え“出版バブル”と呼ばれた。そんな時代に売れに売れていた本や雑誌には、ある共通点が存在するという。文芸評論家の三宅香帆氏が、当時の人々の読書志向を解説する。※本稿は、三宅香帆『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社)の一部を抜粋・編集したものです。
