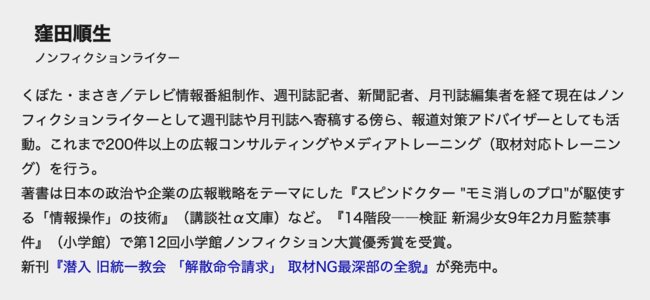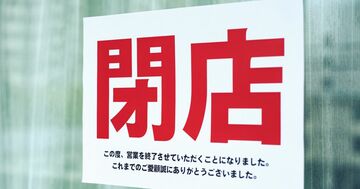しかも、この規範意識を養う教育は「三つ子の魂」ではないが、小学校入学前から行われることが定められている。
「集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと」(幼稚園の目標 第二十三条二)
このような規範教育を受けた子どもがどんな大人になるだろうか。マジメに学校に通っていた子どもほど、会社からの理不尽な命令にも喜んで従う「社畜」になるのではないか。誤解を恐れずに言えば、日本の学校教育というのは「優秀な社畜」の大量生産システムなのだ。
人口が増えて経済も好調な時はこのシステムはプラスに働いた。しかし人口が減って経済も冷え込むと逆回転していく。社畜があふれるような組織は、与えられたルールに従うだけで、新しい付加価値を創出することもできないし、イノベーションも生まれないからだ。
だから、日本のビジネスの効率性を上げていくには、まずはここを変えていくしかない。日本の「規範意識教育」を変えて、「ルールで縛る」という昭和のマネジメントから脱却をしなくてはいけないのだ。
「教育が悪い」というと、「左翼」などと叩かれてほとんど話を聞いてもらえないのだが、私は企業危機管理の仕事をやっていて、社長などの経営陣と打ち合わせをすると、びっくりするほど「学校教育」を引きずっていることに気づく。つまり、「どんなに理不尽なことであっても、組織が一度決めたルールに従うのが当然だ」という考えに縛られている。
昭和的な教育を受けた経営者や管理職が
「ルール縛り」を繰り返す負の連鎖
また、部下などにパワハラや暴力をふるうような管理職と話をすると、「会社のルールを守らないあいつが悪い」「みんなに迷惑をかけたから、これくらいやられるのは当然」などと学校のイジメっ子のようなことを平気で言う。さらに話を深く聞くと、学生時代に教師や部活の顧問に殴られて育った人も多い。
人は知らず知らずのうちに、自分が受けた教育を次世代に繰り返す。パワハラを受けて一人前になった人は、管理職になれば下にパワハラをしてしまう。それと同じで、子どものときから「理不尽なルールに従う」ということを強いられていた人は、経営者やマネジメント層になると、組織全体を理不尽なルールで縛ろうとする。
そういう「負の連鎖」を断ち切らない限りは、日本の競争力はどんどん低下していく一方ではないかだろうか。
(ノンフィクションライター 窪田順生)