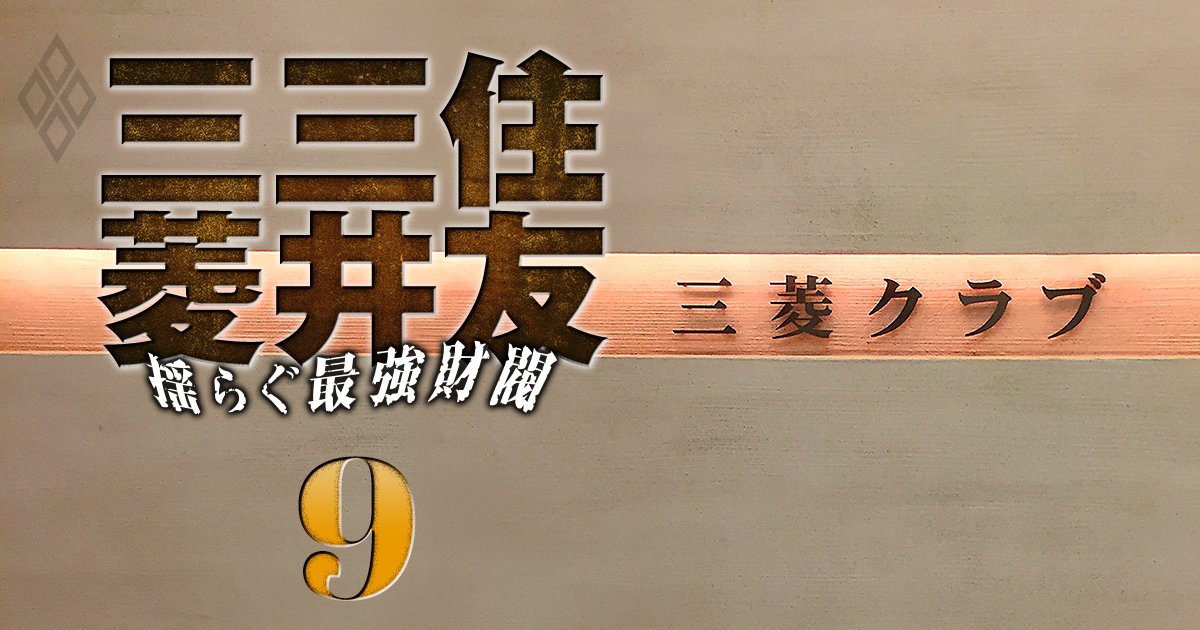量子技術の理論は難解で、そのテクノロジーをわかりやすく説明するのは専門の研究者でも容易ではありません。しかし、量子技術を応用した量子コンピュータは、高速演算できるスーパーコンピュータでも難しいとされるシミュレーションや、機械学習、組合せ最適化問題(複雑で膨大な選択肢から最適な解を導き出すこと)などを一瞬で処理できるようになると期待されています。また、量子コンピュータは、省電力であることなどの長所があり、実用化が進められています。では、量子技術を社会実装していくうえで必要なことは何でしょうか。
量子力学は古典的な物理学、つまり目に見える論理合理的な科学法則が通用しません。量子は、観測されるまでは粒子でもあり波でもある、つまり0でもあり1でもある、異なる性質のものが共存している世界です。理論物理学者のエルビン・シュレーディンガーは、これを「シュレーディンガーの猫」と呼ばれる例えで説明してきました。猫と毒ガス発生装置を密閉された箱に入れた状態だと、その中の猫は生きている状態と死んでいる状態の両方が共存する──難解に聞こえるかもしれませんが、生命活動の中ではこうした量子力学的な動きは普通に起こっていることです。たとえば、コマドリが地磁気を感知して移動するのも、植物の光合成が最適な経路で行われているのも、量子力学で説明できます。
私は量子について話す際、よく大乗仏教の思想である「唯識(ゆいしき)」を例に挙げます。唯識とは、モノも人もコトもすべては心の産物であるという考え方です。たとえば能の舞台には、セットが何もありませんし、能面は表情を変えません。しかし、能楽師の動きによって能面は悲しい表情にも見えるし、笑っているようにも見える。唯識論では、このような人間の心の動きを「存在はあるのでもなく、ないのでもない」と表現します。こうした矛盾を排除する二元論的思考が通用しないという点で、量子力学と共通するところがあります。
唯識論では、人間は8つの「識(しき)」でできているとされます。眼、耳、鼻、舌、身(触覚)、意という意識の層と、エゴや煩悩の源泉となる末那識(まなやしき)や心の根底を成す阿頼耶識(あらやしき)という、あらゆる人間に共通する無意識の層です。根本の識である阿頼耶識にはさまざまな業(ごう)や煩悩が種子(しゅうじ)という形で溜め込まれます。これを熏習(くんじゅう)といいます。こうした種子を浄化すれば、自他を分けるエゴイズムは生まれず、分別することが可能になります。
さらに、阿頼耶識は個人を超えてほかの人とつながることができます。個人の修行はその人一人だけのものではなく、ほかの誰かを救うこともあるという考え方です。
少々ややこしい仏教思想の話が続きましたが、これをテクノロジーの文脈に置き換えると、阿頼耶識はクラウドのようなものと考えられます。多くの人やモノがインターネットを介してつながれば共通認識が形成され、そこに倫理が生まれる。そうなると特定の人が、故意に誤った情報や偏ったデータを用いてAIを学習させようとしても、思うようにはなりません。AIが分散化されて多様性を実現することが、恣意性の解消につながるわけです。ただしそのためには、正しいデータ、事実に基づいたデータが要求されます。つまり、データを浄化された状態にすることなのです。その代表が、モノやインフラから得られるデータです。人間が入力するのと違い、恣意性が入り込む余地がないため、不正確なものはほぼ存在しません。この膨大なサイバーフィジカルのデータを扱うために量子コンピュータが必要となってくるのです。
プラットフォームとしてのDXで
効率化・高度化を超える
2024年5月に、東芝は経営再建に向けた長期ビジョン「東芝再興計画」を発表しました。その中でも、量子技術による変革をQX(quantum transformation)と名付けて目標に掲げています。ただし、量子技術にはまだ課題が残されており、一足飛びに進展しそうもありません。どのようなステップでQXを実現していこうとお考えですか。
デジタル技術を基盤とする社会経済は、DE(digital evolution)とDX(digital transfor-mation)を経て、多様なプラットフォームが業界を超えてつながるQXへと発展すると考えています。一般的には前の2つをDXと一くくりにしがちですが、既存のバリューチェーンやモノづくりを効率化、高度化するDEと、そこから生まれるデータをさまざまなプレーヤーと共有して価値を生み出すDXは、本来は区別する必要があります。
私たちはDXを、エコシステムを構築するためのプラットフォーム戦略ととらえています。企業や組織の壁を越えてネットワークでつながり、リアルタイムでデータを共有し、共鳴することで、データの価値は飛躍的に高まります。DEとDXの実現を後押しするのが「ソフトウェア・デファインド」という考え方で、これは文字通り、ソフトウェアが価値を定義する、という意味です。従来はハードウェアの中にソフトウェアを組み込み、一体となって機能してきましたが、ソフトウェア・デファインドでは、逆にソフトがハードを包み込んで制御、操作することになります。アプリケーションを追加したりデータを更新したりするなどして、付加価値の継続的な向上が可能になります。
たとえば東芝には、エレベーターの制御盤をクラウドに接続することで、クラウドから制御ソフトの書き換えや更新を可能にするサービスがあります。運行状況の確認をはじめ、ファンやエアコンの操作がリモートでできるほか、清掃や警備用のロボットが自由にフロア間を移動することも可能です。また、スマホのアプリを使ってワンタップでエレベーターを呼び出すサービスは、車いすをご利用の方やお体が不自由な方にも好評です。クラウドにつながることでエレベーターの機能が拡張され、進化したといえるでしょう。これはほんの一例ですが、ソフトウェア・デファインドには何気なく利用しているインフラや、大した機能は備わっていないと考えられてきた端末の価値を一変させる可能性があります。ソフトウェアがプラットフォームとなり、自社だけでなく他社も含めた多様なハードやアプリが接続され、そこから得られるデータを活用して新たな価値を創造する。これが東芝の目指すDXです。そのためには技術や製品の一部をオープン化して、誰でも自由につながれるようにすることが重要で、参加者が多いほどネットワークの価値は高まります。
つながればつながるほど価値の高いデータが集まる点も、ハブとしては魅力的です。プラットフォームの阿頼耶識化といえますね。
その通りです。恣意性を排除したファクトデータが得られるとなれば、その価値は計り知れません。ですから、私たちが提供する製品、技術、インフラシステムなどで、ソフトウェア・デファインド化を粛々と進めているところです。サイバーの世界ではGAFAがデジタルデータを独占していましたが、フィジカルデータとなると話は別で、私たちが築いてきた資産や技術が最大限に活かせると考えています。POSシステムの分野でトップシェアを持つ東芝テックが手がける「スマートレシート」も、サイバーとフィジカルの融合によるDXの一例です。通常は紙で提供されるレシートを電子化して、データとして管理・提供するサービスです。ユーザーはレシートで財布を膨らませることなく、いつどこで何をいくらで買ったかなどの購買データをアプリで管理できます。導入店舗では、紙のレシートの発行コストや環境負荷を低減できます。2023年度は約5600万枚、稚内とパリの距離に相当する長さのレシートが削減できました。
さらに従来はレジ集計や在庫管理、マーケティングなど、事業者ごとに活用されてきたデータを、メーカーや小売企業、メディアなどと連携し、統計データとして社会全体で活用することが可能です。現在の会員数は200万人を超え、購入金額や数量などの購買データは政策立案などにも寄与しています。
その際、私たちが何より重要視しているのは、個人のデータはあくまでもその人のものであることです。本人の同意は当然必要ですし、データがどこにつながるのかを完全に見える化して、たとえばこの会社には自分のデータを渡したくないと拒否することも可能です。そのうえで、本人がデータを活用したりコントロールしたりできる環境を整え、自分の行動がデジタル化されて情報がつながるメリットをユーザーが実感できることが大切だと考えています。