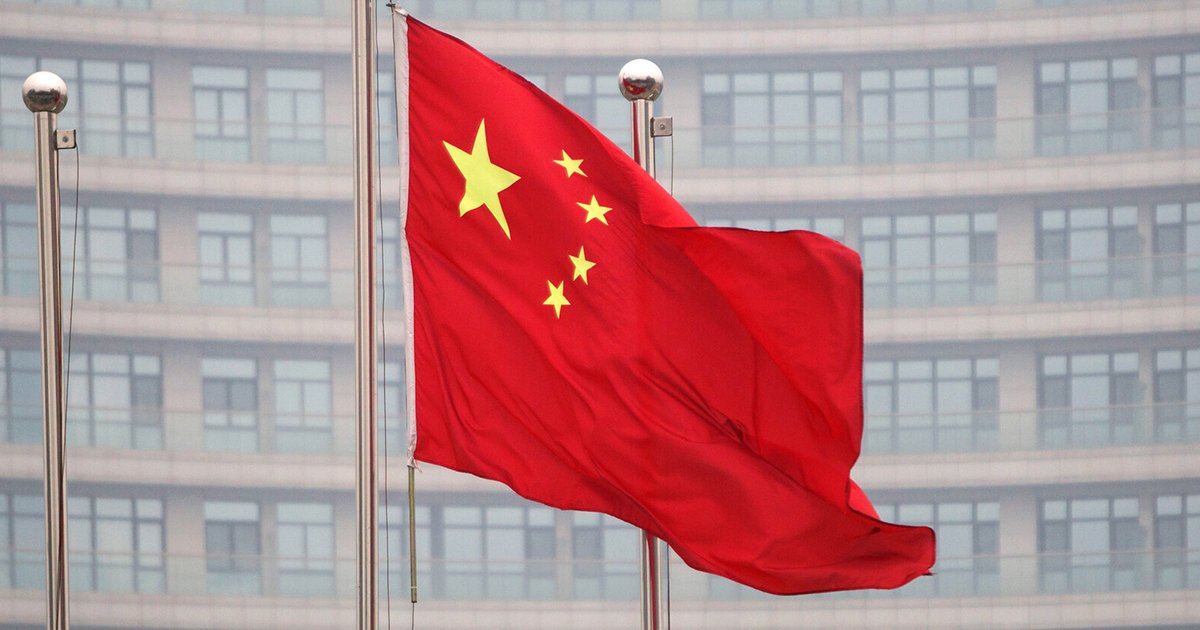 Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
少子高齢化の進む中国。1人っ子政策の廃止後も出生率は低下し続け、人口は2021年をピークとしてついに減少に転じた。2012年に中国共産党のトップに就いた習近平は、かつて「中国の夢」(=中華民族の偉大な復興)を語っていた。西側の多くの知識人も、中国はいずれ米国を追い抜くだろうと熱視線を送った。だがいま中国の夢は、夢のまま終わりかけている。※本稿は、熊谷亮丸『この一冊でわかる 世界経済の新常識2025』(日経BP)の一部を抜粋・編集したものです。
加速する中国の人口減少
コロナ禍の影響も
国連の「世界人口推計2024年版」によると(以下の同統計の数値は断りのない限り中位推計による)、中国の人口は2021年7月1日時点の14.26億人をピークに減少に転じ、2023年は14.23億人となった。
同推計は2050年に12.60億人、2100年には6.33億人に減少するとしている。これは2022年版の推計よりもそれぞれ0.52億人、1.33億人少ない。
2022年版は2019年版から同様に0.90億人、2.98億人引き下げられていた。つまり、わずか5年の間に合計でそれぞれ1.42億人、4.31億人も下方修正されたことになる。
この主因は、合計特殊出生率(1人の女性が生涯で産む子どもの数)がここ数年で大きく下がったことだ。中国の合計特殊出生率は1998年の1.52を当時のボトムに緩やかに上昇し、いわゆる「1人っ子政策」が完全に廃止された2016年の翌年である2017年には1.80に上昇した。
しかし、その後は低下傾向を強め、2020年は1.24、2023年には1.00に低下した。当然、2020年以降の低下はコロナ禍によるところも大きい。2022年末まで3年にわたった「ゼロコロナ」政策下では、都市ごとにロックダウン(都市封鎖)や厳格な移動・行動制限が繰り返された。
景気下振れ圧力が強まり、雇用や所得への不安が継続しただけでなく、妊婦検診や出産・入院などにも悪影響が及んだ。中国は2023年初からウィズコロナ政策に転換したが、(1)妊娠期間を考えると、政策転換の効果(出生率向上)はすぐには表れないこと、(2)不動産不況により家計のバランスシート調整が始まるなど、将来の経済的不安が高まっていること、などにより、2023年も合計特殊出生率の低下が続いた。
さらに、将来の合計特殊出生率の推計も大幅に下方修正された。2019年版では2020~2050年の合計特殊出生率は平均で1.73、2051~2100年は1.76と想定していたが、2022年版は2050年までの平均を1.30、2100年までの50年間の平均を1.45、2024年版ではそれぞれ1.11、1.28と推計している。
「1人っ子政策」廃止後も
低下する出生率
コロナ禍の影響は中期的なものにとどまると想定され、合計特殊出生率の大幅下方修正には、より構造的な要因が横たわっていることになる。
1つは産児制限緩和の効果が限定的なことだ。人口大国の中国では、資源や食糧確保の観点から、1979年以降、世界でも類を見ない極めて厳格な産児制限が実施された。







