分岐点に立つ日本
東山魁夷画伯の代表作の一つに「道」という作品がある。草原の中を一筋に伸びた道。なだらかな坂を青空に向かうようでいて、少し右に曲がっている。その先は見えない。
高校の現代国語の教科書で、ご覧になった方も多いだろう。筆者もその一人だ。いまでも東京で勤めている大学院の近くにある国立近代美術館に足を延ばしては、この絵の前にたたずむことを楽しみにしている。もっとも、最近は展示される機会がないようで、また見られるのが待ち遠しい。
解説によると、「これから歩もうとする道」を描いたものだという。1950年の作。戦後の混乱から歩み出そうとする日本人にとって、未来への希望を暗示してくれる絵だったに違いない。
それから4分の3世紀たった現在、我々の前にはどのような道が開かれているのだろうか。この絵の先にある丘の上に立てば、未来の道が見えてくるはずだ。そして、それは大きく3つに分岐しているのではないだろうか。
1つ目は、ひたすら高い空に向かって真っすぐ進む道。しかも勾配はますます急になる。デジタル勝ち組が唱える「指数関数的成長」に向かう道だ。いずれ天に届いてしまうかもしれない。もっとも「リミットレス」(限界なし)という強者の思想は、天すら突き破ってしまいかねない。
2つ目は、左に大きく曲がって、来た方向に逆戻りする道。アメリカの生態学者レイチェル・カーソンが、名著『沈黙の春』の中で、「未踏の道」と呼んだ脱成長に向かう道だ。このまま成長を続けると地球は破綻する。したがって多くの環境論者や社会主義論者は、成長志向そのものに封印をして、「ウェルビーイング」な世界に安住すべきと説く。
そして3つ目は、東山魁夷画伯の絵のように右に曲がって方向を変えていく道。量から質へと成長の次元をワープすることを目指す。成長か非成長かというデジタルな二択ではなく、「異成長」という第三の選択肢を模索する。
真の「未踏の道」とは、単に現状に留まることでも、元の道を引き返すことでもない。もちろん「けもの道」でもない。それはけものたちが、自分たちのリスクとリターンを考慮に入れて、秘密裏につくり上げた利己的な道にすぎない。
安易な選択肢を避け、道なき道にみずから踏み出していかなければならない。そうすることによって、我々の後に正しい道ができるはずだ。
第2回へ続く
◉構成・まとめ | 宮田和美(ダイヤモンドクォータリー編集部)
【新刊のご案内】
名和高司氏の最新刊『シン日本流経営』(2025/2/18発行)は
こちらでご購入いただけます。
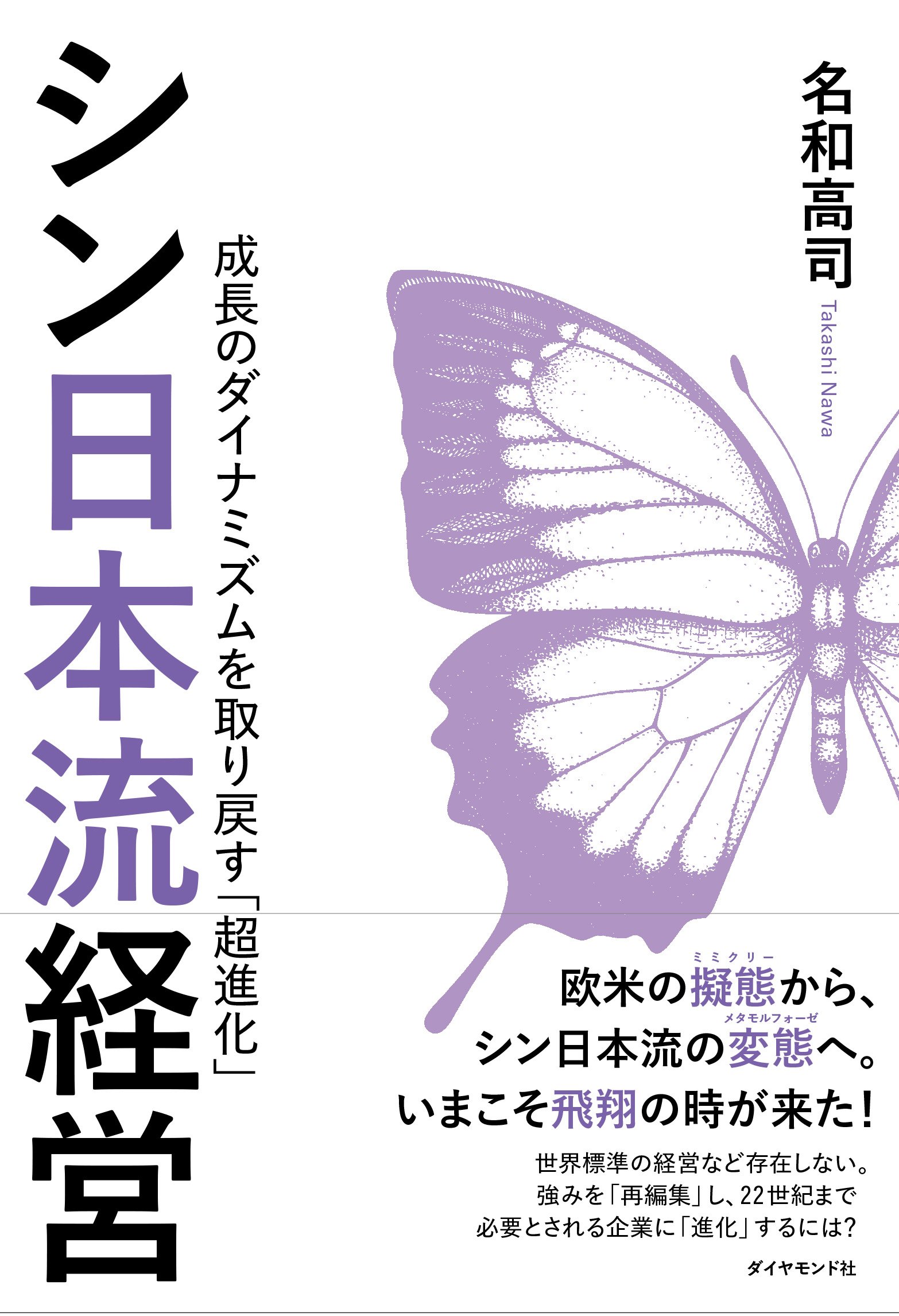

![[検証]戦後80年勝てない戦争をなぜ止められなかったのか](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/9/8/360wm/img_98a65d982c6b882eacb0b42f29fe9b5a304126.jpg)





