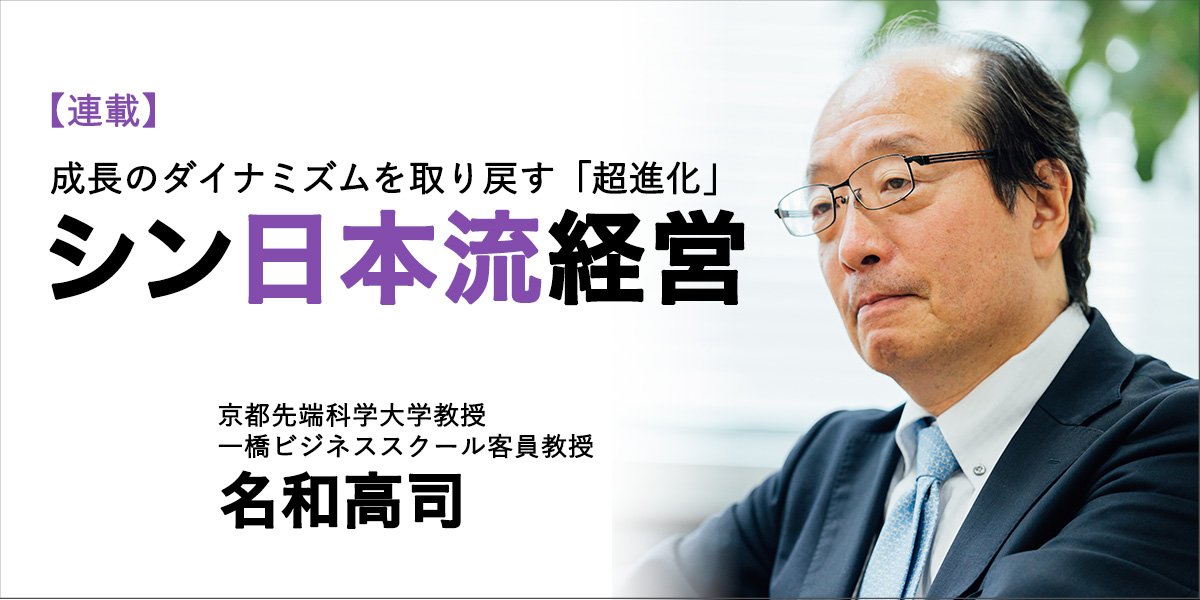
なぜいま「シン日本流経営」が必要なのか──
日本流経営は優れた元型を持ち、利他心、人基軸、編集力という日本ならではの「本(もと)」を軸に守破離を繰り返し、世界で存在感を示してきた。では、なぜ多くの日本企業がそれを見失い、平成、令和という2つの時代を通じて競争力を低下させ続けることになったのか。
「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と持ち上げられたのもつかの間。バブル崩壊とともに一気に自信喪失に陥り、アメリカ流の株主至上主義に思い切り舵を切っていった。日本流を封印し、「世界標準」モデルを取り入れようとした結果が、平成の失敗を招いてしまったのである。
そもそも世界標準というものは、世の中に存在しない。取り返しがつかなくなる前に、我々は日本流の本質を取り戻し、それを「シン日本流」にアップデートさせる知恵を発揮しなければならない。
「失われたX年」という
負のスパイラルから脱する
日本が元気を取り戻している。
「失われたX年」などという自虐的なムードに、いつまでも閉じこもっている場合ではない。マイナス思考からプラス思考に転換すれば、明るい未来が実現できる。これを社会心理学では「自己成就的(じこじょうじゅてき)予言」と呼ぶ。根拠がない思い込みをもって行動すると、結果的に本当に実現できてしまうというのだ。
とはいえ、いったん停滞を経験した日本は、自分に対して疑い深くなっている。自信を取り戻すためには客観的な根拠がほしい。
 名和高司 Takashi Nawa
名和高司 Takashi Nawa京都先端科学大学 教授|一橋ビジネススクール 客員教授
東京大学法学部卒、ハーバード・ビジネス・スクール修士(ベーカー・スカラー授与)。三菱商事を経て、マッキンゼー・アンド・カンパニーにてディレクターとして約20年間、コンサルティングに従事。2010年より一橋ビジネススクール特任教授(2018年より客員教授)、2021年より京都先端科学大学教授。ファーストリテイリング、味の素、デンソー、SOMPOホールディングスなどの社外取締役、および朝日新聞社の社外監査役を歴任。企業および経営者のシニアアドバイザーも務める。著書に『学習優位の経営』(ダイヤモンド社、2010年)、『パーパス経営』(東洋経済新報社、2021年)、『稲盛と永守』(日本経済新聞出版、2021年)、『資本主義の先を予言した 史上最高の経済学者 シュンペーター』(日経BP、2022年)、『桁違いの成長と深化をもたらす 10X思考』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2023年)、『超進化経営』(日経BP 日本経済新聞出版、2024年)、『エシックス経営』(東洋経済新報社、2024年)など多数。
そのような手がかりの一つとして、「国家ブランド指数」(NBI)に注目したい。世界最大の世論調査会社イプソスが、60カ国を対象に、「輸出」「ガバナンス」「文化」「人材」「観光」「移住と投資」という6つの切り口から世界の世論を調査した結果を毎年発表している。日本は毎年着実に順位を上げ、2023年、過去最高の6年連続で首位をキープしていたドイツを抜き、ついに首位に立ったのである。
個別の項目で目を引くのが、「製品の信頼度」と「他のどの場所とも異なる」という点において、1位を獲得している点である。前者は納得感が高い一方、後者は意外に感じられるかもしれない。日本人は自国の世界標準からの逸脱を、「ガラパゴス化」と呼んで自嘲してきた。しかし、均質化に向かう世界の中で独自性を保っている日本は、みずからの稀少価値をもっと肯定的に評価してもいいのではないだろうか。
もっとも、昭和世代は、そう手放しで喜んではいられないかもしれない。半世紀ほど前、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」とおだてられて、「その気」になった経験が思い起こされるからだ。その頃が頂点で、その後、日本が下り坂を転がり落ちていった苦い記憶が甦ってしまう。ただ、その当時なぜナンバーワンといわれたのかを、しっかり振り返ってみてはどうだろうか。
『ジャパン・アズ・ナンバーワン』の著者のエズラ・ヴォーゲルは同書の中で、日本の高い経済成長の基盤は、日本人の学習への意欲だと分析している。そして皮肉なことに、この学習能力に変調を来したことが、平成の失敗に結び付いてしまったのだ。
成長が頭打ちになる中で、日本企業の多くはこれまでの日本流経営を「昭和型」と切り捨て、アメリカ流経営に大きく舵を切った。そして、マイケル・ポーターの競争戦略に代表される、一見切れ味のよさそうな経営論を次々に学習していく。リエンジニアリング、ビジネスモデル・イノベーション、ROIC(投下資本利益率)経営など、枚挙にいとまがない。
しかし、そのような理論先行型の経営モデルは、実践知を重視する日本企業の現場に実装されることはなかった。日本流の現場の強みは軽視され、最新理論で武装したはずの経営が迷走を繰り返す。このような表面的な学習、すなわち「擬態(コスプレ)」経営が、平成の失敗の本質である。
この失敗は、令和にも持ち越されようとしている。ガバナンス、両利きの経営、ジョブ型などを「世界標準」と崇めて取り込もうとする擬態が、留まるところを知らない。しかし、そもそも世界標準などというものは、どこにも存在しない。卑屈な島国根性が生んだ幻想でしかないのだ。北欧諸国やシンガポールなど、成長を続ける国々の企業は、それぞれ独自の経営モデルに磨きをかけている。
当のアメリカですら、欲望資本主義を基軸とするアメリカ流経営を抜本的に見直そうとしている。そのような中で、数周遅れの擬態学習にすがっていたのでは、いつまでたっても「失われたX年」という負のスパイラルから脱することはできない。
20世紀型の競争優位は、先が読めないVUCA時代には通用しない。筆者は20年前から、「学習優位」を次世代経営モデルとして提唱してきた。その本質は学びに徹するだけでなく、それを乗り越えて、新たな地平をみずからの手で拓くことにある。この「学習」→「脱学習」→「超学習」のサイクルこそが、21世紀の経営のカギとなるはずだ。
そして、それを日本流に言い換えれば、「守破離(しゅはり)」という流儀そのものである。古来、日本人が芸道や武道で大切にしてきたこの日本流をいかに未来に向けてアップデートし、経営に実装するか。それが「シン日本流経営」の基本テーマである。
日本が元気を取り戻したからといって、いまさら昭和型を復活させようという話にはなるまい。かといって平成型の擬態経営を続けていたのでは、いつまでたっても世界のフロントラインには立てない。
進化の本質は、過去から未来を紡ぎ出していくことにある。経営の次元に応用すれば、「日本流」から「シン日本流」への経営OSのバージョンアップが問われることになる。
そのためには、まず日本が伝統的に培ってきた強みと、未来に向けた可能性をしっかり見極めることから始めなければならない。経営用語にすると、日本企業が持つ「秘匿」資産と、「未実現」資産の棚卸し作業とでもいえよう。

![[検証]戦後80年勝てない戦争をなぜ止められなかったのか](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/9/8/360wm/img_98a65d982c6b882eacb0b42f29fe9b5a304126.jpg)





