「水ダウ」も「電波少年」も
欽ちゃんが生み出した流れの中にある
日本のテレビは、戦後、1953年に本放送が始まった。新興産業だったテレビは、後発のメリットを生かして思いのままに突っ走った。自由なエネルギーがそこにはあった。
しかし、1970年代にもなると、報道は報道、ドラマはドラマ、お笑いはお笑いというようにきっちりとした棲み分けができてしまっていた。ジャンルの厚い壁が生まれていたのである。それを壊し、ジャンルの既成概念にとらわれずもう一度自由なテレビを取り戻そうとしたのが萩本欽一だった。
『欽どこ』は、まさに「ドラマと笑いがくっついた番組」だった。さらにほかにも萩本は、大胆な実験を試みていた。1979年に放送された日本テレビの『欽ちゃんドラマ・Oh!階段家族!!』。これは、「ドラマって、いつも横に動いてる。人間が縦になるドラマはないの?」というなんともユニークな発想から生まれた。
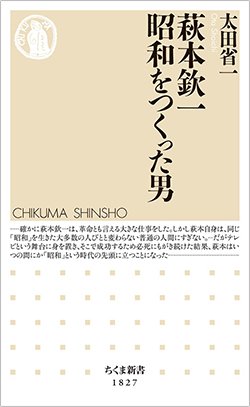 『萩本欽一 昭和をつくった男』(筑摩書房)
『萩本欽一 昭和をつくった男』(筑摩書房)太田省一 著
通常のドラマでは、登場人物が1階から2階に移動する際、途中の階段を上るシーンはカットされる。だがあえて階段の移動を映し続けるのはどうか。そうして生まれたのが、コント作家役の萩本が階段を上り下りしている途中でコントを思いつき、それが劇中で演じられるという型破りのドラマだった(齋藤太朗『ディレクターにズームイン!!――おもいッきりカリキュラ仮装でゲバゲバ……なんでそうなるシャボン玉』日本テレビ放送網、2000年、275頁)。
ここでもドラマとお笑いが結びつき、ジャンルを超越した番組が生まれている。そして萩本が君塚良一に対して予言したように、その後テレビにおけるジャンルの壁は本当に崩れ始めた。
例えば、1990年代になると、猿岩石による「ユーラシア大陸横断ヒッチハイク」が社会現象となった『進め!電波少年』のような番組が人気となる。それをきっかけにドキュメンタリーとバラエティという一見水と油のジャンルを結びつけた「ドキュメントバラエティ」が定着していく。いま人気の『水曜日のダウンタウン』(TBSテレビ系)なども、間違いなくかつて萩本欽一が生み出した流れの中にある。
テレビの娯楽番組の歴史は、「欽ちゃん」登場以前と以後に分けられると言っても過言ではないだろう。萩本欽一は、掛け値なしにテレビに革命を起こしたのである。







