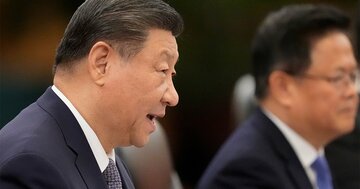「四小龍」「六小強」…中国AI業界が“戦国時代”に突入
近年、中国のAI業界の拡大は目を見張るものがある。例えば、中国の検索エンジン最大手・百度(バイドゥ)の関連企業は「文心一言」という人工知能チャットボットを開発した。そして今年中に、このチャットボットを基礎とする「AIスマートグラス」(ウエアラブル機器)を投入する方針だ。
また、同様にテンセントも大規模言語AIモデル「混元」を自社開発し、推論応力を高めている。通信機器大手のファーウェイは「盤古」を開発し、自動運転や人型ロボットに搭載した。アリババは、自社AI「通義千問」が「世界をリードする性能を発揮し、ディープシークや米メタを超えた」と発表してもいる。
「AI四小龍」と呼ばれる新興勢の成長も著しい。センスタイム(言語AIモデル名は「センスノバ」)、クラウドウォーク(同「従容大模型」)、メグビー(顔認証AI「Face++」を開発)、イートゥー(同「ドラゴンフライアイ」を開発)は資金調達を行い、AIの開発体制を拡充している。特にイートゥーは監視カメラシステムで知られるが、クラウド上にある音声認識、機械翻訳、文書作成AIをマウス操作で利用可能にしたのが特徴だ。
似たような表現で「六小強」と呼ばれる企業、すなわちムーンショットAI、バイチュアンAI、ミニマックス、智譜AI、01.AI、ステップファンも注目を集めている。一例として智譜AIの言語モデル「GLM-4-9B」は、誤答抑制機能で米オープンAIやグーグルを上回ったと報じられた。
要するに、ディープシーク以外にも中国製AIは急増中である。AIモデル開発の一分野については、「中国は米国を上回っている」との見方もある。
米情報技術・イノベーション財団(ITIF)によると、2023年のAI関連研究論文執筆本数のトップは、中国国務院直轄の研究機関である中国科学院だった。2位が、習近平国家出席の出身校である清華大学、3位が米スタンフォード大学、4位がアルファベット(傘下にグーグルなど)、5位が上海交通大学だった。
中国政府は、経済と社会への統制強化のためにもAI開発を重視しているようだ。政府の指示に従順で、政権批判をしない企業経営者には手厚い支援を与えている。そうした政策の下で、大手からユニコーン企業までAI関連分野の成長は加速している。