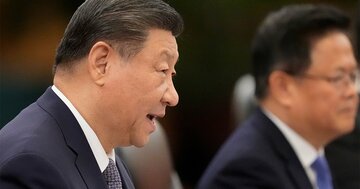中国に優位性を保つ米国企業、「半導体」がカギに
ITIFによると、AI研究論文の引用件数では米国が中国を上回った。引用数のトップはアルファベット、第2位はカリフォルニア大学バークレー校だ。「研究の質」の点では、米国のAI業界は世界で優位性を保っていると言える。
こうした状況を支える重要なファクターの一つが、米国の半導体設計・開発力の高さだろう。ディープシーク創業者の梁文鋒氏は、「高性能半導体の確保が課題」との見解を示している。今のところ、中国の半導体産業の実力は米国に追い付いていない。
現在、中国最大のファウンドリーである中芯国際集成電路製造(SMIC)の製造能力は、回路線幅7ナノメートル(ナノは10億分の1)である。オランダのASMLによる極端紫外線(EUV)露光装置を、中国側は調達できないため、良品率は低いといわれている。
ASMLは米国の知的財産を活用し、最先端の半導体製造装置を供給している。米国の製造技術、知的財産が重要なのは、ファウンドリー世界トップの台湾積体電路製造(TSMC)にも当てはまる。
2月上旬、オープンAIのサム・アルトマンCEOは、専用のAI端末に加えて独自の半導体開発に取り組む考えを示した。日本企業に連携強化を呼びかけたところに、同氏の半導体事業への本気度の高まりが感じられる。
半導体の製造や検査装置、感光材やシリコンウエハーなど、高純度部材の製造技術において、日本企業の競争力は高いからだ。アルトマン氏はそうした要素技術を取り込むことで、ChatGPTのために、より精度の高いチップを作ろうとしているのだろう。中国のAI企業にとって、日米企業の連携はそれなりの脅威になるはずだ。
世界最先端の基礎研究の積み重ねにより、米国はAI分野での競争力を高めてきた。民間の大手企業もデータセンター投資を拡大し、オープンAIをはじめ成長は加速した。
エヌビディアとトヨタ自動車が連携したように、AIで全く新しい需要を創出する成長の兆しは増えつつある。重要なことは、そうした前向きな変化が、マクロ経済に本格的に浸透するかどうかだ。