車内放送についても変化が見られる。全国的に、車掌が乗務しないワンマン化が進み、自動放送が導入されたことで、肉声による案内放送は急速に減っている。地方私鉄や第3セクターは言うまでもなく、JRでも、北海道や四国、九州では、都市部を除いて列車の大半がワンマン化されている。当然、車掌による、味わいのある肉声のアナウンスは少なくなっている。
過去のものとなった
売り子の声と車内販売
駅弁は今も昔も変わらぬ人気を誇っているが、多くは売店での販売となり、なかにはコンビニで購入しなければならないケースも増えている。かつて、ホームに響きわたっていた売り子たちの声は、ほとんど過去のものとなってしまった。
車内販売も減少が著しい。2023(令和5)年10月をもって東海道新幹線からワゴンによる車内販売が終了となり、“走る喫茶室”の伝統を誇った小田急電鉄のロマンスカーも、2021(令和3)年3月のダイヤ改正でワゴンサービスが終了となった。新幹線に限らず、在来線でも車内販売の売り子の声を耳にすることはほとんどできなくなっている。
車販スタッフの独特な言い回しやフレーズは消滅寸前であり、車端部の離れたところからやってきて、脇を通り過ぎ、そして離れていくという音量の変化も体験できなくなりつつある。これもまた、記録しておきたい音の風景である。
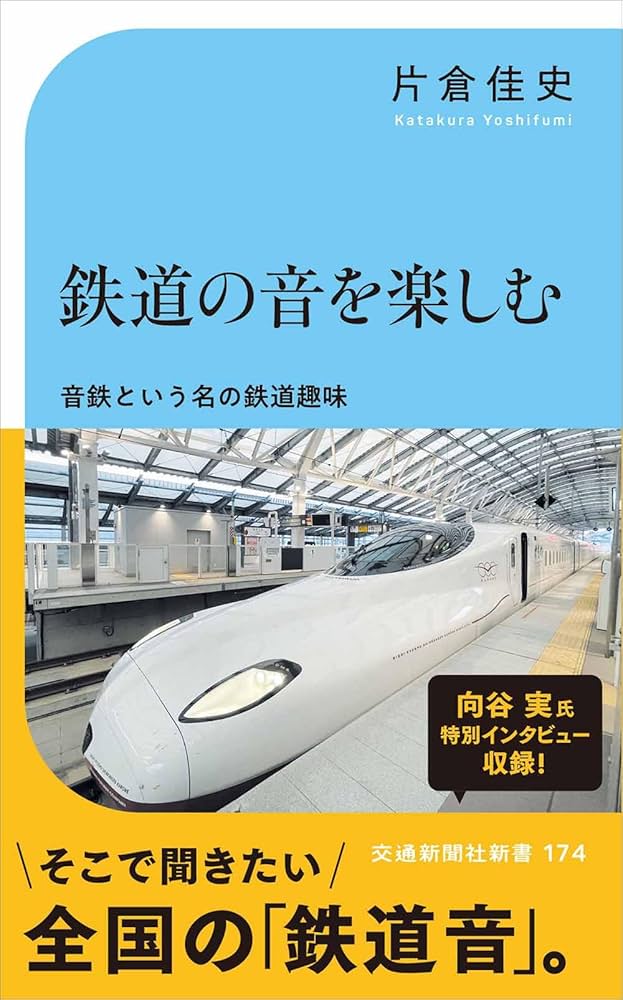 『鉄道の音を楽しむ 音鉄という名の鉄道趣味』(片倉佳史、交通新聞社)
『鉄道の音を楽しむ 音鉄という名の鉄道趣味』(片倉佳史、交通新聞社)
さらに、ローカル線の廃止や地方私鉄の経営不振、厳しい収支状況に苦しむ第3セクターの鉄道会社など、明るくない話題が多い昨今だが、それでも鉄道は地域住民の足として、立派に機能している。こういった鉄道の車内放送や乗換案内、運転士と駅員のやりとりなどを記録しておくと、かけがえのない音源となるだろう。高校生を満載した朝夕の車内音も、その土地や歴史を知るうえでの重要な記録となっていくはずだ。
これらのデータはきっと何年かしたら、往時を偲ぶ貴重な音源になる。その姿を臨場感たっぷりの「音」で記録したいところである。
※なお、“音鉄”趣味を楽しむにあたり、







