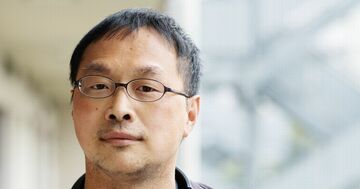どれも壮絶な内容で目を疑う読者もいらっしゃると思いますが、日頃受ける相談内容や見聞きしていることから考えると、事実かどうか疑う余地はありません。
ハラスメントが減らないことの大きな要因として、相談先がないことが非常に大きいと考えられます。
ハラスメントを受けたとき誰に相談したかを質問すると(複数回答、251名)、ほとんどが家族・友人・知人(65.7%)、所属先・現場の関係者(50.2%)でした。
専門家(医師カウンセラーなど13.1%、弁護士・社会保険労務士8.0%)、第三者機関である自治体などの相談機関(6.4%)や、労働組合や所属する団体(6.4%)、警察(4.4%)に相談した人は限られています。解決につながりやすい、加害者が所属する会社などの相談窓口に行った人も5.6%と非常に少ないです。
「相談してもムダ」「不利益が怖い」
芸能界ハラスメントが放置される理由
相談しなかった理由は(複数回答、255名)、相談しても解決しないと思った(66.7%)や、相談することで人間関係や仕事に支障が出ることを恐れていたり(63.5%)、不利益をこうむる恐れをもつ人が約半数(47.8%)いました。そもそも相談先がわからなかったり(36.5%)、被害による精神的ショックから話せる状態になかった人(25.9%)や、証拠がないから諦めた(21.6%)といった人も多いです。
被害が多いわりに相談できていないことが非常にアンバランスで、解決の糸口がなかなか見えない実態が明らかになりました。
では、どうしたらよいのか。回答(複数回答、416名)にはハラスメント防止対策や解決方法の提案として、ハラスメント研修(67.3%)や相談窓口の周知(64.2%)、契約書の明示(56.5%)などがありました。他にも発注側に相談できる窓口を設置する案(38.0%)やアンケート調査の実施(28.8%)を求めています。
たとえば、「抜き打ち調査や個別の聞き取りをする」「こういう業界だからという内外のイメージを払拭する」「規則や労働基準を明確に決めておく」「加害者の氏名の公表」「アンガーマネジメント講習の実施」「メディアを横断的に監査する仕組みを作る」「加害者の報酬の減給や解雇」「加害者に病的症状である場合は加療を義務にする」などの意見もありました。