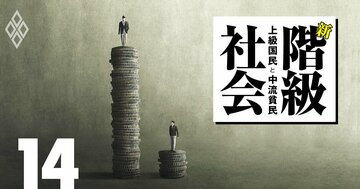資産が生み出す収益は
経済成長よりも大きい
ピケティが正しければ、おもに20世紀後半に観察された比較的平等な状態は、戦争と破壊という犠牲を通じてもたらされた例外的な期間だった。
この主張をもってピケティは、米国人経済学者のサイモン・クズネッツの考えに異を唱えた。クズネッツは、富の格差は歴史的に“釣り鐘型の曲線”の形で発展してきたと考える。最初は平等で、次第に不平等が増して少数派が富を独占するが、その後、技術の発展により経済成長の果実がより多くの人々に行き渡るようになるので不平等が次第に減っていく(注3)。
一方のピケティは、これまでの歴史を通じてずっと、財産から得られる利益のほうが、経済の成長を上回っていたと主張する。この考えをピケティは単純な「r>g」で言い表した。
資産が生み出す収益(r)は経済成長(g)よりも大きいという意味だ。これが正しいのなら、社会経済的な不平等は積極的な再分配で是正しない限り、必然的に拡大を続け、長期的に安定することになる。その行き着く先は、富める者に富が集まる、いわゆる「マタイ効果」だ。
最近では、オックスファムなどの非政府組織によって、年に数回は世界規模の不平等にスポットライトが当てられている。2020年時点で、全世界における富の偏りが次のように表現されている。「世界で最も裕福な22人の男性がアフリカに住むすべての女性(数にして3億2500万人)を合計したよりも多くの富を独占している(注4)」。
このような主張には、反論がないわけではない。たとえば、個人の純資産、つまり負債を差し引いた資産に重点を置いた場合、150万ユーロの住宅ローンを抱えているロンドン市民は、蓄えもないがその代わり借金もないジンバブエの人よりも貧しいことになる。そうは言っても、富の蓄積とわずかな国のわずかな地域において収入の急上昇により、物質的な偏りが過去に例のないほど拡大したことは事実だ。
注4 https://www.oxfam.org.uk/media/press-releases/worlds-22richest-men-have-morewealththan-all-the-women-in-africa