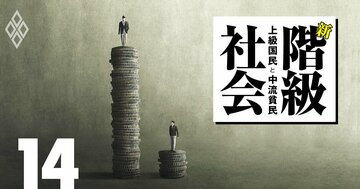社会的特権の世代間継承を
阻止することは不可能
グスタフ・シュトレーゼマン(編集部注/ワイマール期ドイツで首相・外相を歴任)の義理の兄弟にあたるクルト・フォン・クレーフェルトが、1918年、貴族の称号を得た最後のドイツ人になった。
まもなく可決されたワイマール憲法109条にはこう書かれていた。「出自もしくは地位にもとづく公法上の特権や不利益は廃止される。貴族の称号は姓名の一部とみなされ、今後一切授与されることはない」。これをもって、ドイツにおける社会格差の源が過去のものとなった。
その一方で、特定の社会経済的階級への帰属を示す、より繊細な形の要素が数多く存在する。
とりわけ、ピエール・ブルデューが繊細な格差について書いた興味深い大作『ディスタンクシオン(注6)』が、社会的な差異がいかに個人のハビトゥス(性向)の形で具現化されるかを示している。
ハビトゥスが外部シグナルおよび行動指標となって、個人がどの社会集団に属するかが示唆される。ある人が社会からどう認識されるのかを決める要素として、特に重要になるのは文化資本だ。
食事のマナー、クラシック音楽への造詣、ロンドンにあるあまり有名ではない博物館や美術館に詳しいか、話し方はどうか、イントネーションや方言があるか、どこでどんな暮らしをしているか、服装はどうか、ディナーパーティーの席でほかの人々を相手にワインやビンテージ時計やバウハウス派建築家や印象派絵画やファミリーオフィスやラテンアメリカ文学の魔術的リアリズムなどの話が滞りなくできるか。そうしたことが、個人がもつ文化資本の量を決める。
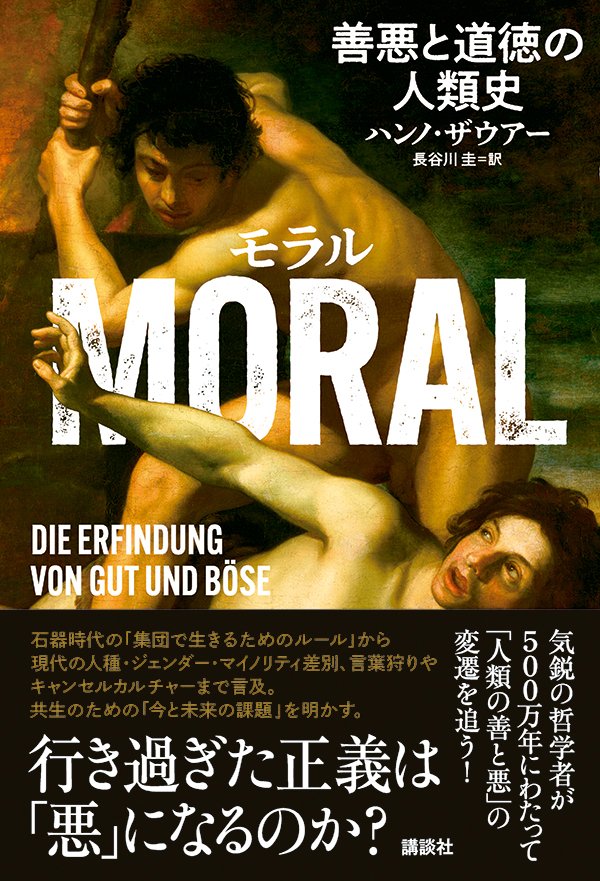 『MORAL 善悪と道徳の人類史』(ハンノ・ザウアー著、長谷川 圭訳 講談社)
『MORAL 善悪と道徳の人類史』(ハンノ・ザウアー著、長谷川 圭訳 講談社)
この種の「支配的知識」を身につけるには、若いころからなじんでいなければならないので、そうしたことの教育に熱心な家庭で育った人は、格別に有利な状況にあると言える。スタートダッシュでついたこの差を政治の力で埋めるのはほぼ不可能だ。ある人物の生活様式とハビトゥスを決める行動規範は暗黙的に洗練および継承されるものであって、介入によって単純に操作できるものではない。
たとえ、ある社会が物質的には完全な平等を実現できたとしても、社会的特権の世代間の継承を阻止することは不可能だろう。それどころか、経済的な意味での平等が広がれば、繊細なステータスにおける格差は逆に悪化すると考えられる。
なぜなら財産という点で野暮な大衆と同じ立場になったエリートたちは、自らを際立たせるために、たとえば難しい言葉を多用するなど、繊細なステータスシンボルの強化に全力を尽くすに違いないからだ。