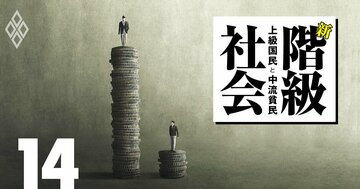現在のエリートが
次のエリートを決める
社会経済的な不平等は不正義の1つの側面に過ぎない。権力や財産などといったリソースの分配が偏っている状態が不当か否かは、その社会の歪みの程度だけでなく、その社会におけるステータスの移動がどの程度可能かによっても決まる。誰にも権力や富や地位を手に入れるチャンスがあるのか、格差が乗り越えようのない壁として化石化しているのか、という問題だ。
つまり、社会的な格差だけでなく、社会における「流動性」も問われている。不平等は一度確立してしまうと、驚くほど頑固だ。当然だろう。今日のエリートが、誰が明日のエリートになるかを決めるのだから。
基本的にそれは自分の子であり、ステータスを重視する親はときに驚くほどの熱心さで、ピアノのレッスン、博物館巡り、乗馬教室、外国語授業、あるいは家族資産の整理などを通じて、子供たちにエリートとして生きていくための準備を施す。
スコットランドの経済学者グレゴリー・クラークは珍しいファーストネームをもつ人の家族の社会的地位を数世代にわたって追跡することで、現代社会の透過性を調査している(注5)。
たとえば、「ペピーズ」が歴史の舞台に初めて登場したのは1496年、ケンブリッジ大学の学生としてだった。それ以降、50人以上のペピーズが同大学に入学した。統計学的な計算で予想される頻度の20倍以上の確率だ。今も生きているペピーズは18人で、うち4人が医師である。近年に亡くなったペピーズたちは、平均して50万ユーロの財産を遺した。
特に驚くべき事実は、政治の介入をもってしても、社会の流動性にはほとんど変化が現れないことだ。公的教育制度も、義務教育も、大規模な経済成長も、選挙権や市民権の拡大も、税金の再分配も、現代社会の透過性を大きく高める役には立たなかった。
とりわけ、身分階層――誰が上流社会に、誰が下流社会に属するか――などの“ソフトな”形の社会的不平等は、規則として明文化されでもしない限り、事実上根絶できない。身分の格差が法的に決められている場合は、法の改正を通じた廃止もしくは緩和が可能だ。