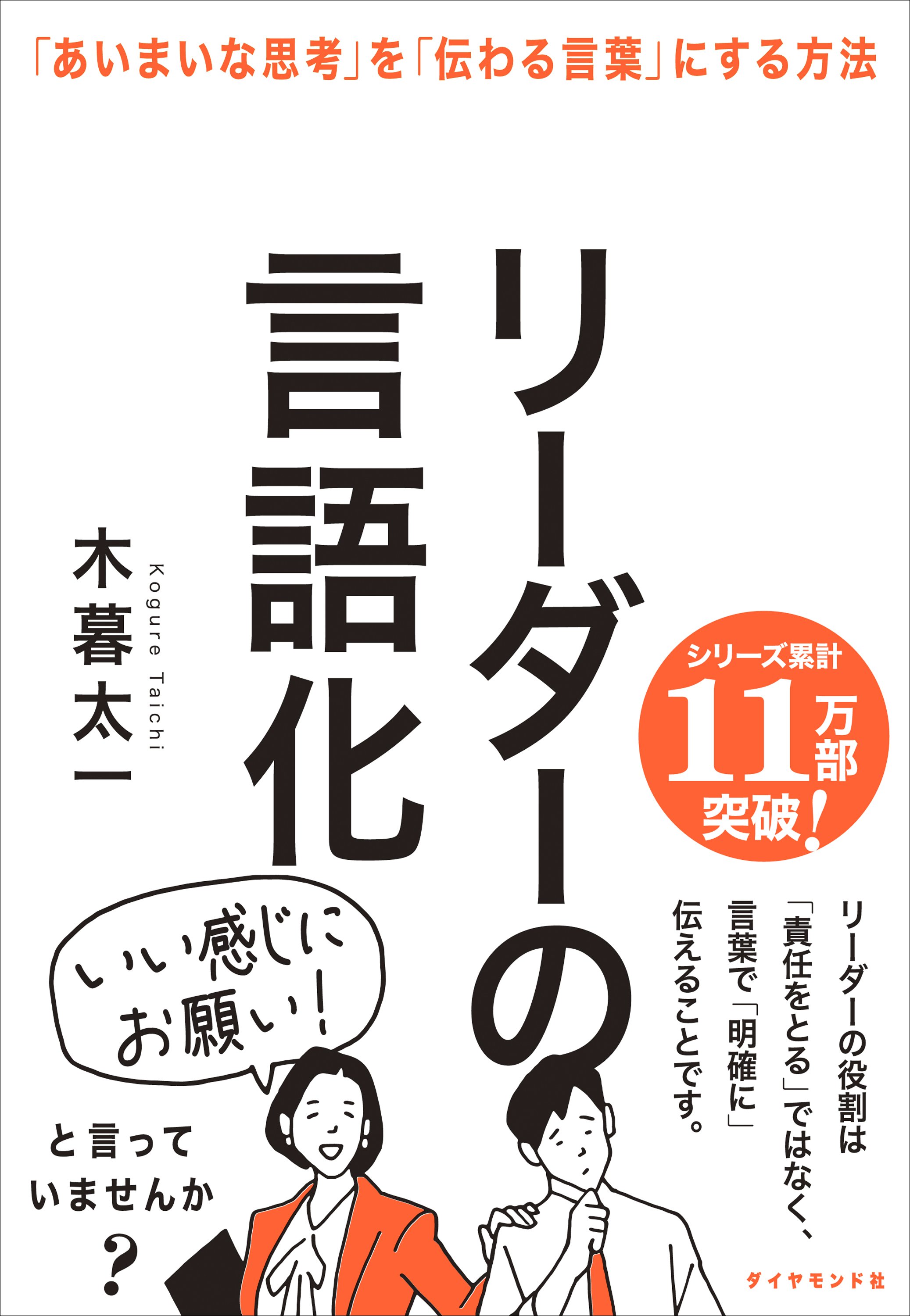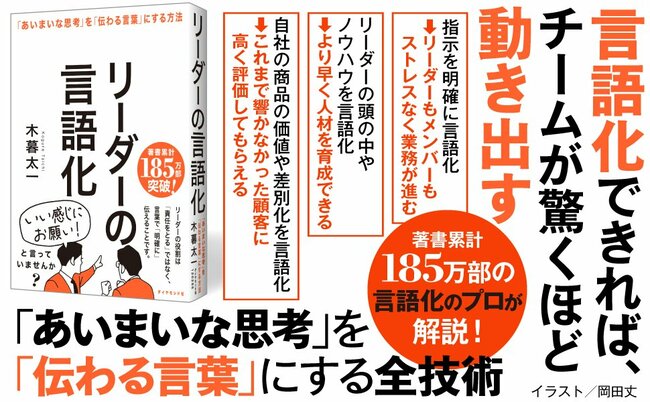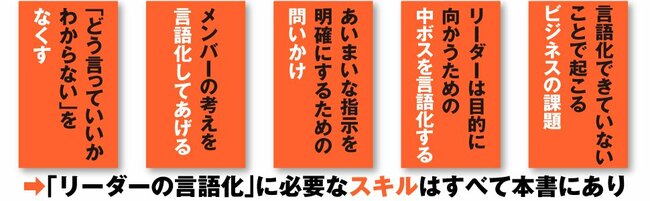「顧客満足度を高めよう」はどう定義する?
「顧客満足度を高める」というゴールが示されたら、リーダーであるあなたはまずこの言葉の定義をします。何が満たされれば顧客満足度が高まったと言えるのかを考え、必要条件としてリストアップするわけです。たとえば、
● 顧客からのリピート発注率が10%上がること
● 新規のお客さんの紹介を依頼したとき、既存顧客の半数が応じてくれること
● 顧客からの商品の使い方についての問い合わせが現状の半分になること
と考えたとしましょう。これがあなたにとっての「顧客満足度が上がった」という定義です。
もちろん、この定義は暫定案です。チーム内ですり合わせたり、経営トップに確認したりする必要が出てくることもあります。ここで大事なのは暫定でもいいからとにかく定義をしてみること、と捉えてください。
「商品のブランディング」はどう定義すればいい?
そして、ゴールの定義は何階層にもわかれることもあります。
たとえば、「商品のブランディング」を経営者から命じられました。このままメンバーに「よし、商品のブランディングだ! みんな動け!」と伝えても、メンバーは何もできません。そこで定義をします。
仮に「ブランディング=30代・40代のOLのうち、過半数が知っている状態」とします。となれば、知名度を上げればいいということが見えてきます。
ですが、まだ終わりではありません。
「よし、対象顧客の半数が知っている状態を目指そう! みんな動け!」と伝えても、まだ動けないのです。
それは「知っている状態」がまだあいまいで、施策を明確に出せないからです。
「知っている」とはどういう状態を指しているでしょうか?「この商品、知っていますか?」「はい、知っています」というレベルでしょうか。
店頭で見て「この商品よく見かけるから売れているのかな」と思ってもらえるレベルなのか、それとも「○○といえば、この商品」とそのカテゴリで即答してもらえる状態なのでしょうか?
どれが正解かではなく、自分がどの状態を意図しているかがポイントです。そして、経営者から示されたゴールが自分の中で明確になるまで、定義を繰り返すということが大事なのです。
それが明確になれば、必然的にやるべきことが明確になっていきます。そして、メンバーに指示することも明確になります。
ゴールを達成するために、これからのリーダーは「言語化」すること、そのために「定義」することを意識しましょう。