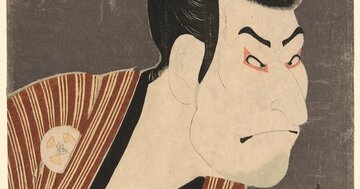意次が目指した財政再建と外交政策
まず、意次が手がけた政策をみてみよう。意次が老中となり幕政の実権を握ったのは1772年、54歳のときである。これをきっかけに意次は自らの政治的才能を開花させ、功利的で重商主義的な政策を次々と打ち出すことになる。
当時、幕府は財政難にあえいでいた。年貢を増やそうにも吉宗の時代に新田開発をやりつくしており、限界があった。そこで意次は商業資本を積極的に利用して財政を立て直そうとした。
株仲間を広く公認して運上金(うんじょうきん)や冥加金(みょうがきん)といった、いわゆる税金をとる一方、銅や鉄、真鍮(しんちゅう)などを幕府の専売とし、さらに鎖国令を緩めて長崎貿易を拡大する開放的な対外政策を行った。具体的には、流出の激しかった金・銀の替わりに銅や俵物(干しアワビ・いりこ・フカのひれ)を輸出し、金・銀の輸入を促進したのである。
さらに、意次の政治家としての資質を象徴するのが、先進的な国土開発計画だ。
吉宗の時代に中断していた下総国(千葉県北部)の印旛(いんば)沼や手賀(てが)沼の干拓事業を商人資本で再開し、新田開発と運河の開削を目指したのである。
蝦夷(えぞ)地(北海道)の開拓計画も壮大だった。北海道の十分の一を開拓して新田畑をつくるという大規模なもので、開拓後はロシアとの貿易までも計画していた。当時はロシアの脅威が声高に叫ばれていた時代で、意次はロシアと国交を結び貿易を行うことで日本を守ろうとした。このことから、当時としては珍しい外国にも目を向けていた政治家であったことが分かる。
意次の評判を落とした後世の史料
田沼意次という人はけっして汚職にまみれた悪徳政治家などではなく、時代を見極め、斬新で進歩的な経済政策、社会政策を実行した優れた政治家であった。確かに商業を重視したため賄賂をもらうこともあったろう。しかし、そのことばかり取り沙汰されるのは「木を見て森を見ず」の類で、意次という人物を正しく理解したことにならない。
意次が稀代の悪徳政治家というレッテルを貼られてしまった背景には、失脚後、幕政の舵(かじ)をとった政敵・松平定信の存在があった。この定信時代に意次像がゆがめられ、悪く伝えられたのである。事実、田沼時代を語る史料のほとんどが後世に著されたものだ。