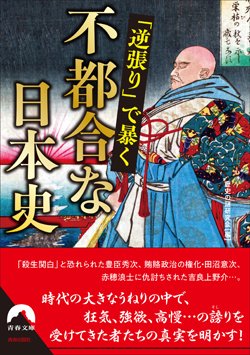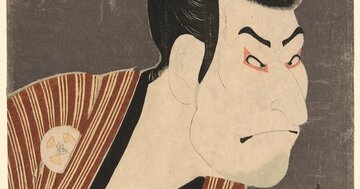意次にしてみれば、相次ぐ自然災害は不運であったに違いない。江戸の大火や浅間山の大噴火に加え、天明の大飢饉も彼の時代に起きている。困窮する一般民衆や下級武士を救済できず、ただでさえ異例の出世を遂げたことで嫉妬の対象であった意次には致命傷となった。
そのうえ1786年には、後ろ盾であった将軍家治の死によって松平定信ら反対派勢力が台頭し、意次は志なかばで政権の座を追われることになる。
田沼意次は時代に先駆けて商業の分かる政治家だったといえるだろう。しかし、これは幕府内では異端に属することであった。そもそも江戸幕府は農業色の濃い政権だった。一般的な学問であった朱子学も農業主義で、武士の間には商業に携わることを卑しむ傾向があった。
そのため頭の固い連中の目には、商業中心で幕府財政の立て直しを図る意次が、商人と組んで汚いことをしているとしか映らなかった。なかでも譜代門閥(ふだいもんばつ)層の反発が大きかった。この反発が、のちの意次弾劾(だんがい)へとつながるのである。
意次失脚後の「寛政の改革」は大失敗
また、賄賂についても意次には言い分がある。確かに江戸幕府は汚職がほとんどない政権だった。しかしこれは、それまで商業との関わりが少なかったからに過ぎない。商業政策を推進していけば、賄賂という行為は当然発生してくるものなのだ。たまたま意次が、商人と深く結びついた幕閣の嚆矢(こうし)となっただけのことである。
意次の失脚後、松平定信が老中となり、意次の政策を全面否定して「寛政の改革」を押し進めた。ところが、結果は散々だった。それもそのはずで、定信が行った改革は現実的な貨幣経済に対応しない倹約一辺倒の古い政策でしかなかった。倹約は消費を冷え込ませるだけであった。
結局、定信の改革は田沼時代に備蓄した資産を食い潰す形でわずか7年で終わっている。確かに人格的には田沼意次より松平定信のほうが高潔だったかもしれないが、政治はそれとは別物である。
「清濁併(あわ)せ呑む度量がなければ、良い政治などできない」。それが真意を理解されず不遇な晩年を送った田沼意次の言いたかったことではなかっただろうか。