あとになって、そんなに重要性の高くないタスクをやっていたり、緊急度の高いタスクが後回しになっていたり、仕事の進行がもっと短い工程で済んだのにと後悔したりすることも少なくありませんでした。
リーダーだからこそ
自分では決められない
「5割強」とまではいかないまでも、自身の仕事がある程度できているリーダーWさんは、毎朝、出社すると仕事を始める前にまず、その日1日の全体の流れとその週の予定を確認しています。
今日は午後1時から3時は「予備時間」にしているから、割り込み仕事が入ったとしてもその時間で対応できる。割り込みが何もなければ、最近、調子の悪い部下〇〇さんの相談を受けられるな、○○さんの都合が合わなければF社の企画案に取りかかれる、などと考えます。
火曜日と木曜日は終日ほとんど時間が取れないから、この日はデスク仕事ができないものとして考えておかないといけない、金曜日の会議の準備は水曜日に終わらせよう、などと確認していきます。
大枠の流れ、過ごし方がつかめたら、それぞれのタスクの全体像を見ていきます。
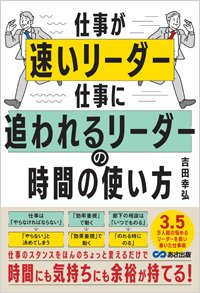 『仕事が速いリーダー 仕事に追われるリーダーの時間の使い方』(吉田幸弘、あさ出版)
『仕事が速いリーダー 仕事に追われるリーダーの時間の使い方』(吉田幸弘、あさ出版)
いわゆる「鳥の目」のように俯瞰(ふかん)的な視点から全体像を把握し、仕事を進めるのに適正な順序(まとめてやったほうがよいもの)や追加対応が必要と想定されるタスク、進めていくうえで出てくる可能性のある事象を挙げていきます。
そして、自分ですべきこと、他の人にまわせることを整理して振り分けます。
リーダーの仕事は、常に量も状況も優先順位も変わります。「自分以外の存在のための仕事」など、自分だけで決められないこともあります。
こうした数々の仕事を最短ルートで終わらせるためにも、本当に幹となる重要なタスクはどれで、枝葉となるタスクはこれで、と全体の工程を見える化して確認する「儀式」をコーヒーを飲みながら行うのです。
この儀式によって、重要度の低い枝葉のタスクに必要以上に時間をかけるのを防止できたり、実は必要のないタスクに気づけたりすることもあります。
やり直しなどの追加の作業も必要なくなるので、所要時間も短縮できますし、「あとどれくらい時間がかかるのだろう」といった、脳をマルチタスク状態にしかねない不安も軽減できるのです。
「儀式」で流れと場を整えることで集中できる







