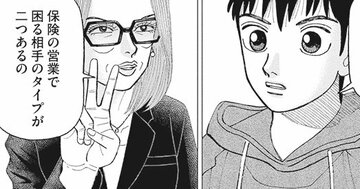亡子の相続で発生しうる
相続税トラブルとは
では、親が亡子の相続をする際、納税資金の他に、どのようなトラブルに直面するおそれがあるのだろうか。詳しくは次の3点だ。
まず1つ目に「相続税の節税が難しい」点が挙げられる。子の相続の場合、親は「配偶者の税額の軽減(配偶者控除)」が使えない。夫婦間での相続の際に高い節税効果がある控除なのだが、残念ながら適用要件を満たさないのだ。この他に適用できる控除や特例を十分に検討した上で納税に臨む必要がある。
2つ目に「遺産の調査が難しいケースが多い」点である。子の世代はスマホやパソコンを使いこなし、ネットバンキングやネット証券で投資を楽しんでいる可能性がある。こうした「デジタル遺産」は預金通帳が発行されていなかったり、スマホのみで投資管理している可能性があるため、親世代には見つけにくい。そのため、子の遺産調査に時間を要する可能性があるのだ。相続税の申告・納付の期限は死亡を知った日の翌日から数えて10カ月であるため、申告に間に合わないおそれもある。
3つ目は「亡子に兄弟姉妹が他にいても、親が存命なら親のみが相続する」点である。亡子の兄弟姉妹に相続手続きの協力を仰ぐことはできるが、相続税の計算に影響を与える「基礎控除額の計算」には法定相続人しかカウントできない。基礎控除の計算は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」である。例として、母1人が亡子の相続人となるケースの場合、基礎控除の計算は「3000万円+(600万円×1人)」であり、受けられる基礎控除額は3600万円に留まる。仮に亡子に兄弟がいたとしても法定相続人には含まれない。
配偶者や子がいない方向け
今から始められる相続対策とは
高齢となった親が悲しみに伏せる余裕もなく相続手続きに翻弄(ほんろう)されることを防ぐためにも、配偶者や子がいない方は事前に相続対策として「終活」を始めることが望ましいだろう。では、具体的にはどのような対策をすべきなのか。
もしも、親以外に遺産を遺したい方がいる場合は「遺言書の作成」が望ましい。特に内縁の配偶者や同性のパートナーと暮らしている場合、法定相続人にはなれないため、原則として遺産を渡すことができない。そのため、遺言書を使うことが有効な方法である。また、日頃からお世話になっている知人や友人、団体への遺贈なども遺言書を使えば行うことができる。親へ遺言書を遺すことも終活として有効だ。遺言書に添付する財産目録には「デジタル資産」も記載するため、親が見つけられずに放置されるトラブルを防げる。