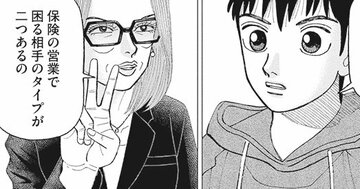また、父母いずれかがすでに死去しており、子が相続人として財産を承継したことがある場合、高額の財産を有している方も多いだろう。この場合、次に発生する二次相続に備えて、対策を開始することが望ましい。一次相続時から税理士に相談しておくことで、二次相続のシミュレーションも可能となる。
次に、相続人による相続税の納税も見据えて対策を進めたい場合は「生命保険への加入」もおすすめだ。生命保険金は審査が終われば速やかに相続人に保険金が送金されるため、相続税の納税資金としても役立つ。生命保険加入時に親を受取人に指定するだけであり、とても簡単な終活だ。生命・死亡保険金には相続税の非課税枠も用意されている。「500万円×法定相続人数」まで控除が受けられるのだ。
また、エンディングノートを活用することもおすすめである。かかりつけ病院の名称や既往症について、友人・仕事関係の連絡先などを残しておくことで、けがや病気による入院時にも役立つ。
知っておきたい
遺言執行者の役割とは
すでに親が高齢であり、相続手続きに翻弄されてしまうおそれがある場合は「遺言執行者」を設定した遺言書を作っておくことを検討してほしい。遺言執行者はまだ広く知られていないが、相続人を代表して遺言手続きを遂行できる人を指す。遺言執行者は遺産の分配や解約、相続登記といった手続きを相続人の同意を得ずとも遂行できるため、高齢の親の負担を減らすことにもつながる。
また、遺言書で親と内縁の配偶者・同性パートナーのいずれにも遺産を分けたい場合、両者が衝突するおそれがある。特に、親へ内縁の配偶者や同性パートナーの存在を知らせていない場合は注意が必要だ。第三者の遺言執行者が手続きを進めることで円滑に遺産の分配が進められる。
遺言執行者は「未成年者及び破産者」を除けば、身近な知人や友人を選ぶこともできる。しかし、金融資産の解約や相続登記などの手続きは法的な知識も必要である。複雑な手続きを一任したい場合は、弁護士や税理士といった専門家に依頼することをおすすめする。特に、生前に親子間で贈与があったり、高額の相続税申告が予想される場合は、あらかじめ税理士へ相談してほしい。