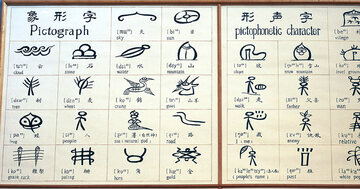孫文や鄧小平が客家の血?
「俗説」の真偽のほどは
客家は円形の土楼のような特殊な住居に住み、犬肉を好んで食べるなどの特異な食習慣や、女性が農作業をする際にかぶる黒い日除け帽子の「涼帽」などの独自の服装を伝えている。すなわち、他の漢族とはまったく異なる特徴を数多く持つ集団とされる――。
「される」が何度も出てきて、読者はうんざりしただろう。もちろん、私がこうした書き方をするのは理由がある。
実はこれらの話の多くは不正確で、学術的にも否定されているからだ。日本で一般に知られる客家のエピソードの大部分は、事実関係が明確ではなかったり、客家に特有ではない(もしくは客家のごく一部にしか当てはまらない)特徴を大げさに強調したりしたものにすぎない。
従来のイメージの誤解を解きつつ、客家の実態に迫っていこう。
まずは革命家や政治家を輩出したとされる「血のネットワーク」だが、そもそもの話として、一般に客家だとされる著名人には、自分自身では客家だと思っていないか、ほとんどそのルーツを意識していない人がかなり多く含まれている。
たとえば、孫文や鄧小平が客家の血を引いていたという俗説だ。孫文の場合は、すこし客家語がわかったという噂に近い話もないではない。だが、前近代の広東人の場合、商業活動などの必要から、母語の広東語と標準中国語以外の方言(潮州語や客家語など)をある程度話せる人はまったくめずらしくない。
孫文の日常言語は広東語であり、両親の世代も含めて客家語で生活していた形跡もなければ、客家のコミュニティに同胞の人脈を持っていた事実も確認されていない。彼の故郷(現在の広東省中山市翠亨村)も客家の村ではなく、仮に祖先の誰かに客家系のルーツを持つ人がいたとしても、孫文自身はほとんど意識していなかっただろう。
つぶさに見れば怪しくなる
客家の「血のネットワーク」
さらに鄧小平になると、客家語を話せたという話さえも伝わっていない。そもそも、鄧小平は四川省の故郷(現在の四川省広安市牌坊村)を16歳で出てから、92歳で死ぬまで一度も村に帰らず、祖先のルーツどころか実の両親に対してすら疎遠な人物だった。
仮に祖先が客家系だったとしても、鄧小平は言語や生活習慣が完全に四川化していたうえ、その故郷や実家すら捨てているのだ。