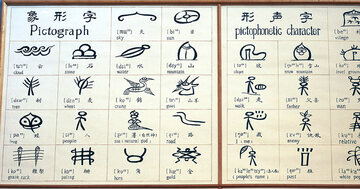たとえば、私が2014年春に広東省東部の掲陽市郊外で取材した李と劉というふたつの宗族(父系の血縁集団)は、長年にわたって隣村同士で対立し、この年の春節(旧正月)にも武力抗争(械闘)をおこなっていた。
現地で長老の話を聞いたり族譜(一族の歴史書)を見せてもらったりしたところ、李一族は唐の李世民の末裔で約600年前に現在の場所に村を作り、劉一族も蜀の劉備の末裔(つまり前漢の皇帝の末裔)で約400~500年前にやってきたと主張していた。
中原をルーツに持つと言う
民族は客家以外にも存在
この李一族と劉一族はどちらも客家ではなく潮汕人だが、祖先は都の長安にいた名族で、その後に南方に下ってきたという言い伝えを持っているのだ(もちろん、当事者がそう信じていることとそれが歴史的事実であるかは別の話である)。
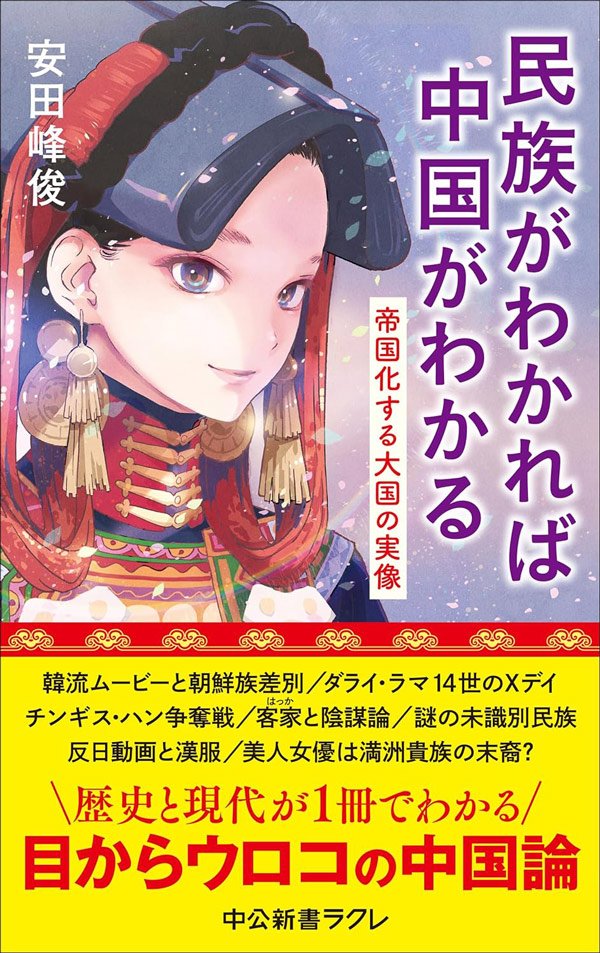 『民族がわかれば中国がわかる 帝国化する大国の実像』(安田峰俊、中公新書ラクレ)
『民族がわかれば中国がわかる 帝国化する大国の実像』(安田峰俊、中公新書ラクレ)
ほかにも華南の各地や海外のチャイナタウンには、宗族の祖先を祀った家廟という施設がたくさんあるが、伝えられている一族の歴史はたいてい「先祖は中原から来た」というストーリーである。さらにチワン族など一部の少数民族にも、祖先が中原の漢人だったとする伝承がある。
日本人の多くが、祖先をたどれば源平藤橘の名家につながると(客観的な根拠はなくても)考えているのと同じく、華南の中国人は、客家系かどうかを問わず祖先のルーツを中原に求めがちなのだ。客家の場合、特定の土地を経由したとする伝承が多いなど一定の特徴もある。だが、伝承の基本的な建て付けは他の華南の漢族と大きくは違わない。