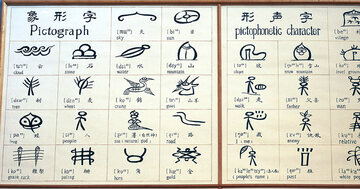いっぽう、リー・クアンユーや李登輝は客家系のルーツを持ち、各人もそれを認めていた。だが、両者はそれぞれプラナカン(マレー化した華人)と福ロー〈ローは人偏に老〉客(ビン南〈ビンは門構えに虫〉化した客家)の家庭の生まれだ。
いずれも、引退後も盛んにメディアの取材に応じるような多弁な政治家だったにもかかわらず、客家のアイデンティティを強調するような言動はあまり伝わっていない。
それどころか、シンガポール人であるリーについては一生を通じて「中国人」という自己認識すらもかなり弱かったと思われる。
彼らは大英帝国や大日本帝国の植民地エリートだったので、リーの母語は英語とマレー語、李登輝の場合は台湾語と日本語だ。「古代の言語を守り抜く」はずの客家の末裔(まつえい)にもかかわらず、両人とも客家語はほとんど話せなかった模様である。
鄧小平はそもそも客家だったか疑問が大きく、リー・クアンユーと李登輝も客家の意識は薄かった。となれば、客家の「血のネットワーク」の同胞意識が中華圏の政治に影響を与えているという話は根本からして怪しくなってくる。
もちろん、客家かそれに近い出身だった革命家や政治家も多くいる。たとえば洪秀全は客家とみられ、太平天国の乱の初期の幹部や兵士にも客家系の人たちがかなり多かった。また、人民解放軍の「建軍の父」朱徳も四川省東部の客家の子とされ、紅軍を率いて広東省の梅州付近に進駐した際に客家語でスピーチしたエピソードが伝わっている。
人民解放軍の重鎮だった葉剣英と、その子で広東省長になった葉選平も梅州出身の客家だ。
喧伝されるエピソードは嘘ばかり
客家伝説の巨大な虚構
ただ、近現代中国の政治変革の震源地になった南方における客家の人口比率がそれなりに高いことや、当時の客家が比較的貧しく、反乱や軍事行動に加わりやすかったことを考えれば、これらについても「血のネットワーク」以外の常識的な説明は可能である。
客家が、他の漢族とは大きく違った文化を持つという話も、実は怪しいものが多い。