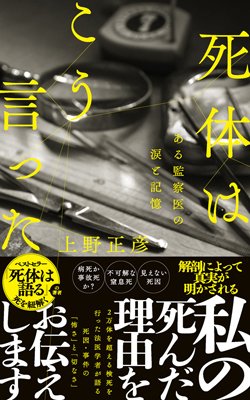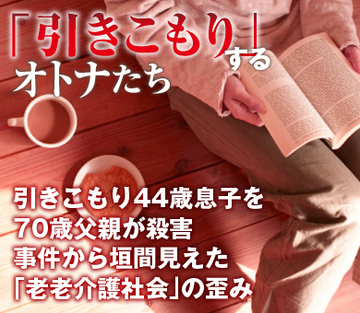しかし、それがどちらなのか分からない。
その判断は監察医と警察にゆだねられる。
この違いによっては、保険に入っていたら保険金の支払いなどが大きく変わってくるため、判断が難しい上に責任重大である。残された状況をきちんと判断し、見極めなくてはならない。
子は親を信じている
担当の警官と議論になった。
警官は「これはこの子が自分で書いたものだから二人とも自殺という扱い」という意見だった。
しかし私はまだ7、8歳の幼い子は「死ぬ」ということがなんなのか、どういうことなのか分かっていないと思えるので、死ぬ意思を持って書いたのではないという意見であった。
「これからお母さんと一緒に逝くのよ」と言われたものの、この女の子はお母さんの言うことの意味が分かっていなかったのではないだろうか。
これが15、16歳であれば、死ぬ意思があったとして遺書として認められるであろうが、まだ7、8歳である。
結局警官と話し合い、まだ成人に達していない子であるから遺書として認めないこととし、子どもは母親に殺された他殺、母親は自殺とされ、母子無理心中となった。
何歳になったら遺書として認めるのかという法律はなく、その場の状況で判断するしかないのである。
こういう事件にぶつかるといつも難しい判断を迫られる。
まだ改善しなければいけないことはたくさんあるが、今は昔に比べ福祉も見直され、障害があって生きることが難しいということは少なくなった。
だが、昔は障害を持った子どもが生まれると親は前途を悲観して無理心中をはかる事件が多く、私も何度もそのような状況での検死の経験があった。
この女の子はもしかしたら、お母さんと楽しいところに出かけられると思って無邪気に書いたのかもしれない。遺書とは思わずに。
子は親が思う以上に親を信じている。どんな親であれ子は親を頼りに生きているのである。
この女の子も母親を信じ切っていたのだろう。その姿を思うと、切なく思わずにはいられない事件であった。
こういう事件が起こるたびに、なんとかこのような親子を救う道はなかったのかと思わずにはいられなかった。
私は、どんな人間にもどんな生き方にも価値があると思っている。誰もが安心して暮らせる国であるよう、日本の未来に期待している。
生きているだけで人間は尊い。