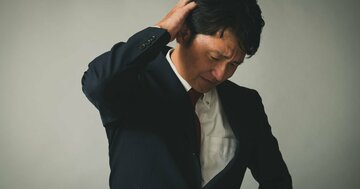ビジネスケアラーの支援は
経営トップ層の理解から
人手不足が加速するなかで、組織を維持するにはビジネスケアラー支援は必須。これから取り組む企業はまず「経営層が介護を知る必要がある」と、石田氏はアドバイスする。
「経産省の『仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン』にもあるように、経営層は仕事と介護の両立施策を行う方針を発信し、全社員が介護を身近に感じる環境作りを行うべきです。また、100~300人規模の中堅企業は、管理職の介護リテラシーも高める必要があります」
会社側が仕事と介護の両立に理解を示すと、介護の悩みを開示しやすくなるという。そうした空気を作り上げたのちに、義務となっている介護休暇制度の設置と、実態把握のための調査、介護に関する基礎情報の発信や研修などの支援策を提供するのがベストだ。
加えて、介護に関する基礎情報の発信や研修など、企業による情報提供も重要とのこと。
「例えば、映像編集・音響効果業を行う株式会社白川プロ(東京都渋谷区)という約300人規模の企業では、介護に関するセミナーの実施や、介護保険料を払い始める40歳を迎えた社員に『仕事と介護の両立 事前の心構え』という小冊子を配布しています。ほかにも、人事部社員を介護相談員に任命し、専門家につなぐ『介護相談窓口』を設置するなど、同社は仕事と介護を両立するための支援に力を入れている企業のひとつです」
親とのコミュニケーションが肝
介護が始まる前の下準備とは
介護関連のサポートに取り組む企業が少しずつ増えているとはいえ、支援体制が整っていない企業も一定数見られている。自分の勤務先で支援が受けられない場合、どのような対策があるのだろうか?
「親の介護がはじまった場合は、自治体や『地域包括支援センター』、かかりつけ医としっかり連携しましょう。何より、一人で抱え込まずに会社や周囲に相談できると、両立の負担が軽くなる可能性があります。また、一人でも声をあげれば、企業がビジネスケアラー(介護と仕事の両立)の支援に乗り出すきっかけになるかもしれません」
ただし、いざ介護が始まると、打つ手は決まっており、選択肢も狭まってしまうのが実情とのこと。それゆえ、もしもの将来に備えて、介護準備に時間を割いてほしい、と石田氏は話す。