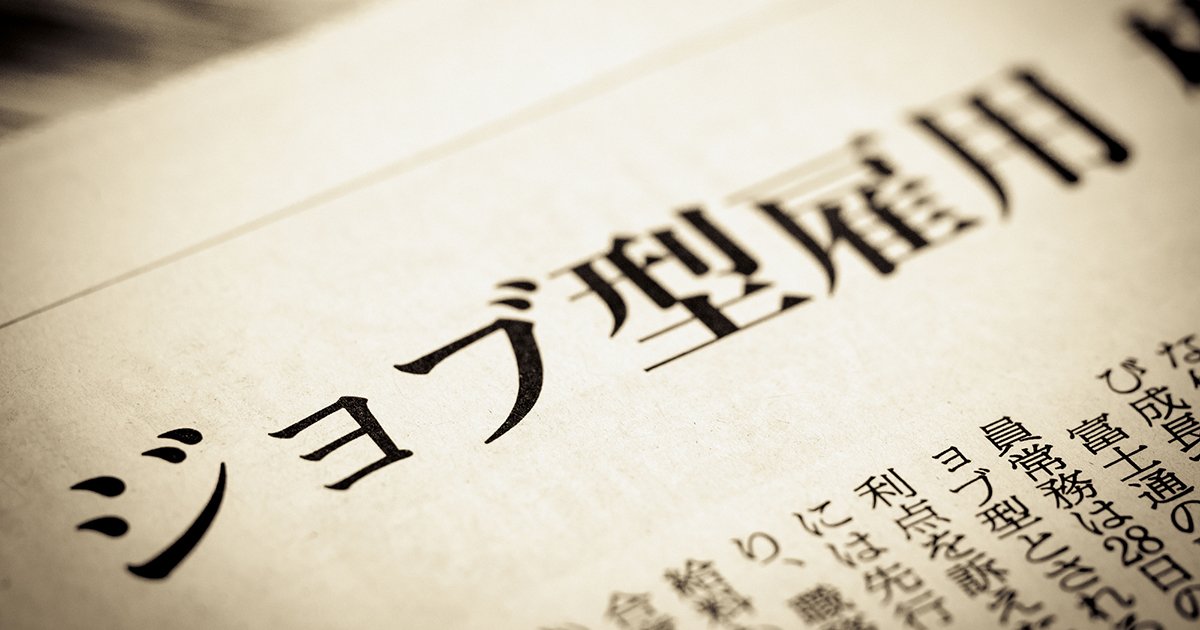 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
日本企業の人事は「ヒト」基準の職能資格制度に基づいていたが、近年「仕事」基準が注目され、ジョブ型の導入が広がっている。労働者の高齢化に起因する、職責と処遇のバランスの見直しが要因の1つだ。経済の活性化に向け、先の岸田内閣が打ち出した「労働移動」は進むのか?企業の生き残る道を専門家が読み解く。※本稿は、藤井 薫『ジョブ型人事の道しるべ キャリア迷子にならないために知っておくべきこと』(中央公論新社)の一部を抜粋・編集したものです。
ジョブ型人事制度は
会社と社員の関係性を変える
わが国の現在の人材マネジメントには、適所適材の配置や職務・職責に応じた処遇という面で弱点があることは否めません。
この先、個別ポジションの職務記述書を整備して、給与は職務給一本、異動はすべて社内公募というようなガチガチのジョブ型(編集部注/企業が職務内容とスキル、経験、資格などを限定して従業員を採用する、欧米では一般的な雇用形態)が主流を占める可能性は低いだろうと考えていますが、大上段にジョブ型を導入するという構えを取らない企業においても、自社の戦略や風土への適合度を考慮しつつ、さまざまなかたちで「仕事」基準を取り入れていく企業が増えるはずです。
たとえば、職能等級と役割等級のハイブリッド型の制度にする、役職登用において勤続年数などの属性条件を一切抜きにした社内公募制にする、特定職種の職種別採用を行う等々です。
筆者は、ジョブ型を制度の趣旨通りに本気で運用すると、企業と社員との関係性が大きく変わっていくだろうと考えています。あえて断りを入れたのは、かつての能力主義や成果主義がそうであったように、ジョブ型も制度の趣旨通りに運用されるとは限らないからです。







