2024年10月の衆議院選挙における自由民主党の公約でも、その方針は引き継がれ、「物価高騰対策・所得拡大」策の1つとして、「物価に負けない賃上げと最低賃金の引上げの加速、地域間格差の是正を図ります。
リ・スキリング、ジョブ型雇用の促進、労働移動の円滑化などの労働市場改革を進めます。正規・非正規雇用の格差を是正するため、同一労働同一賃金を徹底させます」ということで、「ジョブ型」が登場しています。
給与水準が低い企業は
ますます人材確保に苦労する
なぜジョブ型で労働移動が進むのか、ざっくり言うと、仕事ごとの要件と職務給が示されて給与相場が形成されれば、それぞれの労働者が目指すべき仕事が分かりやすくなって労働移動が促進されるという発想です。
給与相場については、市場需要が大きい特定の職種を除けば、ほとんどの職種においては企業横断的な職種別の給与相場が形成されることはないだろうと考えています。
たとえ同じ仕事であったとしても、どの程度の給与を支払うかは、それぞれの企業の戦略判断であり、「仕事」以前の問題として、どの「企業」に所属しているかで給与水準が大きく異なる状況は、今後も続いていくでしょう。
それでも筆者は、ジョブ型によって労働移動が促進されていくのではないかと考えています。
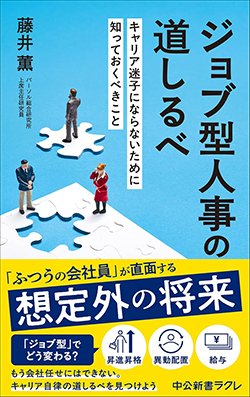 『ジョブ型人事の道しるべ キャリア迷子にならないために知っておくべきこと』(中央公論新社)
『ジョブ型人事の道しるべ キャリア迷子にならないために知っておくべきこと』(中央公論新社)藤井 薫 著
ジョブ型が進んでくると、「ふつうの会社員」の給与は40歳前後で上限に達するようになると予測しています。各等級の給与レンジが狭ければ、それより早く、30代半ばくらいでピークに達してしまうかもしれません。
そこで、その給与水準を許容するか、よりよい処遇を求めてキャリアアップを目指すかですが、育児・教育や住宅購入などの資金需要が大きい世代にとって、昇給の有無や程度は極めて深刻な問題です。
同じ仕事でも給与が高い企業に向けた転職活動を考える人が増えても不思議はありません。給与相場が形成されなくても、むしろ、給与相場が形成されないからこそ、結果的に、労働移動が進むというわけです。
労働力不足は続きます。給与水準が低い企業は今まで以上に人材確保に苦労するはずです。







