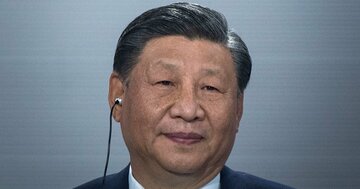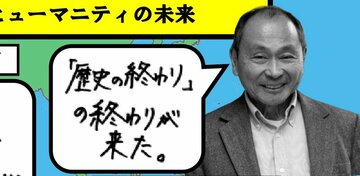そして、トランプ政権1期目に貿易戦争が激化した際には、中ロ両国の関係が「新時代の全面的戦略協力パートナーシップ」に格上げされ、ここ数年は、戦費で苦しむロシアと、新型コロナウイルス蔓延(まんえん)以降の「戦狼外交」で孤立しつつあった中国が、嫌われ者同士、お互いの傷を舐め合う形で関係を深化させてきた。
その完成形が今回の共同声明だ。プーチン氏からすれば「これでトランプ氏に偉そうなことばかり言われずに済む」と実感でき、習近平氏からすれば、台湾統一へと動いた場合、ロシアと強力なタッグが組めるという確信が得られたことになる。
自信を深める習近平氏だが
思い通りにはいかない側面も
貿易戦争に拍車をかけたトランプ関税に関しては、習近平氏は、終始、強気だ。中国のアメリカ依存度よりもアメリカの中国依存度の方がはるかに高いことを熟知しているからだ。
Appleはアメリカで販売するiPhoneの大半を中国で生産しており、戦闘機などに使われるレアアースも大半が中国産。また、アメリカで売られている子ども用玩具もほとんどが中国産だ。中国を敵に回せば、アメリカはiPhoneの製造が滞り、武器も作れず、ハロウィーンやクリスマスに子どもたちを喜ばせることもできない。
とはいえ、海外の軍事基地の数では、アメリカが500カ所以上(米国防総省「Base Structure Report」などによる)確保しているのに対し、中国は正式にはジブチ1カ所だけという現実もある。「それならまず貿易で中国になびく国々を増やし、そのうえで台湾を」と考えるのは自然な流れかもしれない。
もっとも、習近平氏が歴訪した東南アジア3カ国にしても、すべてが中国になびいているわけではない。
マレーシアのアンワル首相は、習近平氏が滞在中、石破茂首相と電話で会談し連携を強化する姿勢を示しており、カンボジアも、習近平氏が帰国した直後、日本の海上自衛隊の艦船の寄港を許可した。