第1に、「現在の所得」を規定するのは「大学時代の学び」ではなく、「働いている現在の学び」であるという点です。「大学時代の学び」が直接「現在の所得」を向上させるわけではありません。
第2に、だからといって「大学時代の学び」が重要でないわけではなく、むしろ「大学時代の学び」が「働いている現在の学び」に大きなプラスの影響を与えることが強調される点です。
つまり、大学時代に学びを積み重ねた人は、働いている現在も学ぶことができ、結果として高い所得を享受しています。
逆にいえば、大学時代に学ぶ習慣がなかった人は、働いている現在も学ぶことができておらず、高い所得を得ることができないということです。学びは膨らんでいくものであり、習慣化させることが大切です。
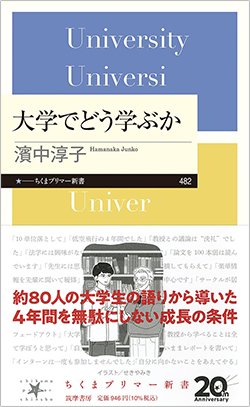 『大学でどう学ぶか』(濱中淳子、ちくまプリマー新書、筑摩書房)
『大学でどう学ぶか』(濱中淳子、ちくまプリマー新書、筑摩書房)
大学時代に学ぶ習慣を獲得すれば、それはその後のキャリアを豊かにする。矢野さんはこのような考え方を「学び習慣仮説」と呼びました。
そして第3に、この「学び習慣仮説」の構図は、どのタイプの大学でも確認できるという点です。歴史のある選抜性の高い大学や比較的新しい小規模な大学など、5つの異なる大学の工学系や経済系の卒業生データを分析したところ、いずれでも同様の結果が得られました。
矢野さんはこの結果を踏まえ、「学校歴のせいにしてはいけないし、いい大学を出たからといって、学習を忘れれば、教育の効果は縮小する。学歴や学校歴だけに囚われず、教育の機会を真摯に活用し、学生の本分を忘れない努力が、将来のキャリアを豊かにする」と述べています(矢野眞和「教育と労働と社会ー教育効果の視点から」『日本労働研究雑誌』588、5-15頁、2009年)。







