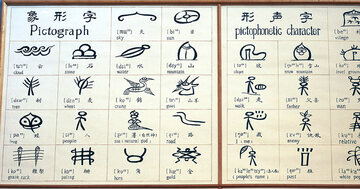「燃やされた軍用トラックなどは私の眼にはどれもみなまったくのポンコツ車に映った。当時の中国ではガソリンは重要管理品目で購入許可証が必要で、市民が簡単に入手できるものではなかった。そのガソリンがいとも簡単に瓶詰めされ、“火炎瓶”となって突如、市内のあちこちに出現した。しかも、おかしなことに北京市内のガソリンスタンドは、どこも暴徒に襲われた形跡はなかった。それではあのガソリンは、一体どこで手に入れたものだったのだろう。今でも私の中ではナゾである」
火炎瓶に不可欠なガソリン
その供給ルートが不明すぎる
渡辺氏の指摘には筆者もまったく同感である。あれほど大量のガソリンを手に入れ、市内各地に火炎瓶として配布するには、相当な組織力と資金力、さらには入手ルートの確保が必要だったはずだ。
だが民主化運動を行う学生たちにも、それを応援する市民たちにもそのような力があったとはとても思えない。むしろ戒厳軍側が、学生市民に対して武力行使をする口実づくりのため、「暴徒が大量の軍用車両を襲撃し焼失させた」という「偽旗攻撃」を演出したと考えたほうが、突如大量の火炎瓶が出現したことを、すんなり納得できるのである。
「暴徒」と軍がつながっていたとすれば、大量のガソリンを入手することなどいとも簡単で、しかも組織的にそれを北京市内各地に配布することも可能だったはずだ。
もちろん軍に抵抗したすべての「暴徒」が軍の回し者であったと、ここで決めつけようとしているわけではない。軍が学生市民に対して無慈悲に発砲し、多くの人がバタバタと倒れるのを目撃した人の中からは、義憤にかられ暴力で軍に立ち向かおうとした人たちも、もちろん存在したのだと考える。
だが、軍を火炎瓶で襲撃した「暴徒」のすべてが、そうした勇敢な学生・市民側の人たちだったとも考えにくいのだ。
投石で逃げた兵士たちは臆病なのか?
それとも確信犯だったのか?
暴徒が軍用車両を襲う光景を直接目撃した渡辺氏は、火炎瓶攻撃の様子についても興味深い内容を記されている。