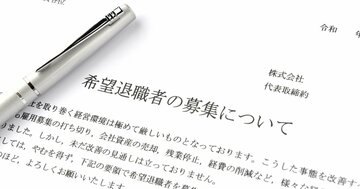写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
「うちの職場、なんかしんどい」――そんな声があちこちで聞こえるようになってきた。しかしそもそも、企業は「コミュニケーション能力」や「主体性」のある人を積極的に採用してきたのではないか。そんなポジティブな人たちが集まっているはずの職場が、なぜつらいものになっているのだろうか。※本稿は、勅使川原真衣『職場で傷つく~リーダーのための「傷つき」から始める組織開発』(大和書房)の一部を抜粋・編集したものです。
テストが得意なだけじゃダメ
学歴神話はもう崩れている
1990年頃までは、「能力」を証明する、と言えば、まずは「学力」でした。「学歴社会」の様相というのはまさに、「学力」=決められたテストでいい点がとれることが、個人の「高い能力」の証明だったのです。
「勉強ができる・勉強をがんばれる人なら、仕事もがんばれるだろう」――これくらいのいわば雑な暗黙の想定に社会全体として合意していたとも言えます。
専門的に言えば「訓練可能性」としての「学歴」が、「能力」の指標として、就職という分け合いの関門に多大に作用すると説明されてきたわけです。
ただそれは、今のみなさんの感覚からすると、「ん?」と思う点が多いのではないでしょうか。「勉強だけできても『使えない』やつが多いしな」などの声が聞こえてきそうです。
それも一理あるかのごとく、能力論は時代とともに変遷していきます。
それも、「仕事ができる人とはどういう人なのか?」「誰が活躍しているのか?」そんな、漠然としながらも、〈できないよりはできたほうがいいに決まってる〉と恐らく多くの人が思っているであろう概念を、アップデートしながら。