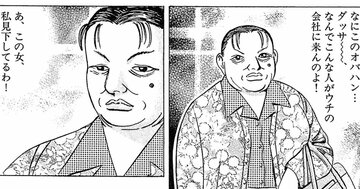新刊『サステナビリティ新時代』は
どのような内容構成になっているか
一方で、この2つのアプローチは未だにSXの具体的な方法論としては確立されておらず、企業やイニシアチブといった各者によって試行錯誤されているのが現状だ。そこで本書は企業が実践しやすい形で2つのアプローチを再構築することに焦点を当てた。本書を読み進めることで、両アプローチの必要性とその具体的な実行手順について理解いただけるだろう。
本書は3つのパートと8つの章から構成される。パート1は理論編(第1~4章)、パート2は実践編(第5~7章)、パート3は業界別事例編(第8章)だ。
第1章では本書全体の中でとりわけ抽象度が高くやや複雑なパート1理論編について、その大きな流れを紹介する。読み進める中で道に迷われた際には、羅針盤として本章に立ち戻ることをおすすめしたい。また、冒頭ではSXに本書から触れる初学者を想定し、「そもそもSXとは何か」といった基礎的な内容もおさらいした。サステナビリティ経営に精通した読者の方々も、復習や知識のアップデートに活用されたい。
第2章では、SXを取り巻く近年の外部環境変化についてまとめた。SXはそのフェーズを新たにしていると先述したが、そうした段階移行の流れを本章で理解してもらえたら幸いだ。また、本書のキーワードであるサステナビリティ課題を統合的に見る「ホリスティックアプローチ」についても概説している。
第3章では、もう1つのキーワードである「システミックアプローチ」の対象となるエコシステムを紹介する。環境・社会課題に関係する社会・産業構造をエコシステムと捉え、その概要と変革の必要性をここでも外部環境の変化をまとめながら紹介する。
第4章は、「システミックアプローチ」の概要と活用方法について紹介する。システム思考で課題を捉え、エコシステムに働きかけることで、課題の根本原因を特定し、解決策を導くダイナミックな変革のイメージをお見せしていきたい。なぜこれらの取り組みが昨今注目を集めているのか、その理由が理解できるだろう。
パート2となる実践編では、まず第5章で、ホリスティックアプローチとシステミックアプローチの具体的な方法論と両アプローチの統合について述べる。それぞれで具体例を紹介しているため、パート1の内容を踏まえながら両アプローチの解像度を一段と高めていただきたい。
第6章では、SXを組み込んだM&Aについて述べる。システミックな変革は社内の変革にとどまらず社外への働きかけが欠かせない。そのため、SXとM&Aの関係性やその直近の趨勢を紹介しながら、システミックアプローチの1つであるM&Aの重要性について解説する。
第7章では、サステナビリティ情報の開示について紹介する。開示は取り組みの成果を企業価値につなげる上で不可欠であると同時に、取り組みを促進する重要な要素ともなる。また昨今のサステナビリティ情報の開示そのものがホリスティックな視点を求めるものに変わりつつある。その動きを追いながら、自社の戦略への統合を見据えていただけるだろう。
パート3(第8章)は業界別事例編として、SXを取り巻く各業界の「トレンド」「課題」「注目事例」を述べる。特に、注目事例ではホリスティック/システミックな取り組みを取り上げた。業界の垣根を超えた連携が必要となるSXにおいて、自社になじみのない業界の事例が新たなビジネスのひらめきの参考となるだろう。自動車、電機、建設、食品・飲料・小売、化学の5業界を取り上げる。
最後に、本書のタイトル『サステナビリティ新時代』について述べたい。環境・社会・経済の持続的成長を目指すサステナビリティはこれまでも、これからも普遍的にすべての企業が取り組むべき活動であることは変わらない。むしろ、気候変動が激甚化し、水不足、生物多様性の損失、人権問題等、多くのサステナビリティアジェンダの懸念が高まっている今、サステナビリティをより力強く、確実に、成果に結びつけなければならない。
「ドラギレポート」も示唆するサステナビリティの理想と現実に真っ向から向き合うことが求められる時代、すなわちサステナビリティ新時代に突入する。そしてそれは、これまでサステナビリティに先行して取り組んできた企業のみならず、すべての企業に等しく訪れる。
本書ではこれから訪れるサステナビリティ新時代の変化に対応し、日本企業が環境・社会・経済価値の創出を最大化するとともにリーディングポジションを得るための方法論を、できる限り実践に足る形でまとめた。また、業界別の取り組み事例をふんだんに盛り込むことで、読者各位の実践イメージが湧くように努めた。これから新時代を生きる読者各位の糧となれば幸甚だ。ではさっそく、本書『サステナビリティ新時代』の幕を開けよう。