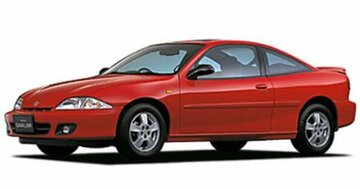なぜ買収コストは割高になったのか
率直に、今回の買収費用はやや割高に見える。日本製鉄がUSスチールに買収を提案した23年12月まで振り返ってみよう。それよりも前に、米鉄鋼大手のクリーブランド・クリフスがUSスチール買収を試みていた。クリーブランド・クリフズが提示した買収額は1株当たり35ドルだった。日本製鉄が提示した同55ドルと比べてかなり低い。
一般的に企業の買収に関して、買収する側よりも、買収される側の方が自社の実情はよく分かっている(情報の非対称性と呼ばれる)。USスチールの内情を熟知したクリフスの買収額を考えると、日本製鉄の提示額は割高と映るだろう。そうした影響もあり買収発表直後、日本製鉄の株価は6%ほど下落した場面もあった。
買収発表後にUSスチールの業績が悪化したことも見逃せない。24年1~3月期以降、USスチールはコストの増加などを要因に、最終損益は右肩下がりで推移した。25年1~3月期、USスチールの最終損益は1億1600万ドル(約170億円)の赤字だった。赤字は2四半期連続だ。
日本製鉄は米国政府の要請に基づいて追加投資も行うので、実質的な買収額は2兆円ではなく3兆6000億円(142億ドルプラス110億ドル)と考えた方が適切だろう。
USスチールの粗鋼生産能力は年間2300万トン程度。粗鋼生産能力あたりの投資額を計算すると、1100ドル(16万円)程度だ。これは、日本製鉄が公開した資料の金額(1トン当たり600ドル、8万7000円程度)を上回る。
鉄鋼業界での買収は、1トン当たりの買収関連コストを1000ドル程度に抑えるのが望ましいとみるアナリストや投資家は多い。その場合、少なくとも10%程度、買収金額は割高と分析できる。今後も米国政府が追加投資を求めることも考えられる。そのリスクからも、今回の買収費用は割高である印象が強い。