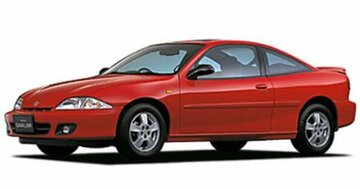日本製鉄の橋本英二会長 Photo:YOSHIKAZU TSUNO/gettyimages
日本製鉄の橋本英二会長 Photo:YOSHIKAZU TSUNO/gettyimages
日本製鉄は株主総会で、買収したUSスチールの経営について株主から「米政府に手足を縛られるのではないか」と質問されると、「米政府に経営を牛耳られるなら、今回の案件はやらなかった」(橋本英二会長)と応じたと報道されている。果たして日本製鉄は割高な買収コストを回収できるのだろうか。(多摩大学特別招聘教授 真壁昭夫)
「日本製鉄は高い買い物をした」の指摘
6月18日、日本製鉄によるUSスチールの買収が完了した。日本製鉄は約141億ドル(約2兆円)で普通株の100%を取得。30日付でUSスチールは上場廃止になった。
日本製鉄の買収の目的は、米国の名門を手中に入れることで鉄鋼業界トップの奪還を目指すことだ。一方、今回の買収劇は米大統領選の時期に重なり、政治的要因から紆余(うよ)曲折した。買収費用は当初の見込み額から大きく膨れ上がった。M&Aの専門家の中には、「日本製鉄は高い買い物をしてしまった」との指摘もある。
日本製鉄は、買収に際して拒否権付きの特別な株式=黄金株を米国政府に与えた。そのため、本社移転や従業員のリストラなどには制約がかかることになる。また、同社は米国政府との合意に基づき追加の設備投資も発表した。その資金を賄うため借り入れは増加し、負債資本倍率(DEレシオ)は上昇する。
今後も鉄鋼業界を取り巻く環境は変化するだろう。組織の統合などを迅速に進め、日本製鉄が持つ高い技術力を駆使して、新生・日本製鉄の収益性を高めることが必要だ。
重要なポイントは、強力なライバルである中国勢にいかに対峙するかだ。彼らは政府の支援もあり、価格競争力を一段と高めるだろう。日本製鉄が独自の技術で新しい製品を開拓できるかが勝負の分岐点になるかもしれない。橋本英二会長をはじめ経営陣の力量が大きく問われる。