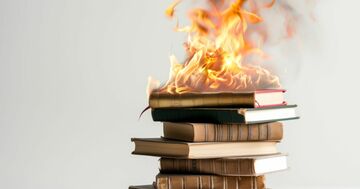明治憲法をめぐる伊藤と大隈の対立
今に続く官学と私学の深い淵源
保守右翼勢力とリベラル勢力が対峙することになった東京帝大の二面性は、当初から計画されたものではなかった。歴史の曲折の中で形成されたことであり、偶然の産物という側面もあった。蓑田のような人物が生まれた背景を考えるには、幕末から明治初期の教育をめぐる事情までたどる必要がある。
当時、教育機関としては、儒学を教える幕府の昌平坂学問所、洋書を翻訳・分析する蕃書調所を起源とする開成所、種痘所を起源とする医学所があった。岩倉使節団の欧米視察を受けて、明治政府はアメリカの自由主義を基調とした学校を千葉県の国府台(現市川市)に設立する構想をまとめたが、西南戦争による財政難で挫折。3つの学問所を継承した3つの大学を作ったが、曲折を経て1877年、「東京大学」を創設して3大学を統合した。
この過程で、国学と漢学が対立して衰退し、洋学が主流となった。「大学」の名称は、7世紀の天智天皇時代、官僚養成の「大学寮」から採用したとされるが、日本の大学の起源は「洋学中心の官僚養成所」とみることができる。東京大学は学問機関の寄せ集めで実務色が強く、当初、政治性はなかった。86年に「帝国大学」と改組され、変質していく。
背景にあったのは、憲法制定をめぐる自由民権運動の盛り上がりだ。明治政府で実力者の双璧は、伊藤博文と大隈重信だったが、大隈は憲法の早急な制定を主張し、イギリス型の立憲政治を標榜した。伊藤は大隈を性急過ぎると批判して81年、「明治14年の政変」で、大隈を政府から追放する。
大隈は民権政治家として82年に立憲改進党を設立して大衆に訴えかけるとともに、早稲田大学の前身である東京専門学校を設立。慶應義塾の創設者で旧知の福澤諭吉と連携した。