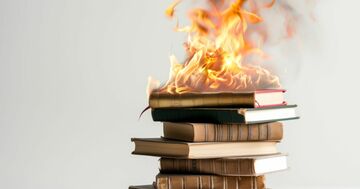天皇は 国家の「主権者」ではなく、「統治の機関」 である。国家の主権は天皇個人ではなく、国家そのものに属する――とする美濃部の天皇機関説は一木から引き継いだものだった。蓑田はこの学説を攻撃したわけだが、それは東京帝大内のもう一つの思想の潮流を意味する。直接の師である上杉慎吉、さらにはその師で、東京帝大法科大学長も務めた穂積八束の教えでもあった。
穂積の思想は「皇位の外に国家なく、国家の外に皇位なし」という「天皇即国家論」をベースにしていた。明治憲法の制定の際、伊藤博文が視野に入れていた立憲君主制への移行や天皇機関説とは食い違う部分があり、学会の非主流派に追いやられたが、穂積は20年以上も東京帝大法学部で天皇絶対主義の憲法を教えた。
上杉は穂積を引き継ぎ、天皇主権説をさらに精緻かつ激しくした。「天皇なければ国家なし。臣民なく領土もなし」「天皇は天神なり日神なり現人神なり」「日本臣民は天皇に服従するを以って基本分となす」などと著書に記している。天皇がすべてあるという主張は、学説というよりイデオロギーやプロパガンタに近いものだったが、蓑田は大きな影響を受けた。
上杉の教え子には、ほかにも戦後首相に就任した岸信介や思想家の安岡正篤らがいる。東京帝大には筧克彦という名物教授もいた。古神道を研究し、畳を敷いた研究室に神棚をまつり、講義は柏手を打ってから始めた。「神ながらの道」を説き、日本は国家も天皇も国民も生活も一つになっていると主張した。蓑田は筧からも大きな影響を受けた。
リベラル派を消した「平賀粛学」とは?
追放された「ファシズム批判」擁護の13教授
こうした大学内での2つの潮流は、軍部が台頭、戦時体制が強まる中で蓑田らの国粋主義の勢いが強まり、東京帝大でも学内の異論の封殺、言論弾圧が強まっていったのだ。その象徴的な事件が「平賀粛学」と呼ばれる1939年の事態だった。
東京帝大の言論事件の舞台は、主に経済学部だった。マルクス経済学を講義するので、左翼思想との接点があった。経済学部の創設は1919年と遅く、自由な反面、派閥争いがあった。法学部のような強固な運営基盤がなかったことも、蓑田らの右翼勢力の攻撃や政府、軍部の介入を受ける素地があった。