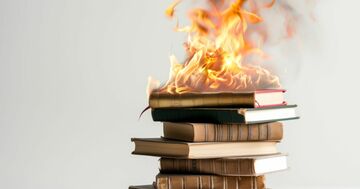一方で伊藤は皇帝が存在するドイツ・プロイセン憲法に範をとった明治憲法を制定し、天皇を「元首」、国民を天皇に支配される「臣民」とする主権在君制で、天皇を神聖不可侵とした。伊藤と大隈の対立は、言い換えれば官権と民権の対立であり、今に続く国立大学と私立大学の存在意義を分ける深い淵源とも言える。
こうした大学の歴史の流れは、東京帝国大にもそれは反映され、欧米文化を吸収する性格と日本的で国家主義的な性格の「二重性」が残されたのだ。それが大学内の言論や思想にも反映され、時に内部対立や亀裂を生んだ。それが蓑田の時代には大きく国家主義へと傾いたと言える。
丸山眞男が看過した「執拗な持続低音」
今も日本に存在する歴史意識の古層
戦争に敗れた日本は、権力構造は大きく変わったが、東京帝大でも同様だった。津田左右吉に東京帝大での講義を懇請した南原繁が45年12月、総長に就任した。
その後を継いだ総長は、『中央公論』に発表した論文で辞職に追い込まれた矢内原忠雄だった。新制東京大はこの2人で戦後の民主的な路線が敷かれた。そして京都大学では滝川事件(1933年)で蓑田ら右翼勢力の攻撃を受け免職となった滝川幸辰が53年、総長に就任した。
蓑田は敗色濃厚になった1944年、故郷に疎開する。敗戦の翌年1月、自殺した。丸山眞男は、蓑田らが抱いた日本人の歴史意識を「執拗な持続低音」と表現している。日本は天皇を中心とした特別な伝統のある国である、国家や政府への異論は極力排除すべきである、危機に先んじて国民を統制する手段を確保すべきである……。執拗な持続低音は、今も歴史意識の古層として日本に存在していると考えるべきだろう。
(文筆家、元朝日新聞記者 長谷川 智)