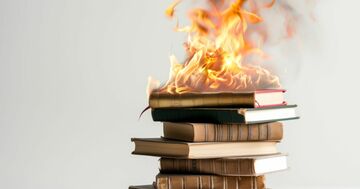経済学部教授だった矢内原忠雄が『中央公論』への寄稿で、議会や軍部、蓑田らの攻撃を受けて37年12月に辞職に追い込まれた。直後の38年2月、教授の大内兵衛、助教授の有沢広巳、脇村義太郎が治安維持法違反容疑で検挙された。共産党関係者らの一斉検挙の一環で、人民戦線事件と言われる。
さらに同年10月には、経済学部教授河合栄治郎の『ファシズム批判』などの著書4冊が発禁処分となった。河合は軍部批判の急先鋒で、天皇機関説事件で美濃部を最も擁護した硬骨の自由主義者だった。しかし、出版法違反で起訴され、休職に追い込まれた。
こうした中で、38年12 月、東京帝大の13代総長に就任し、事態の“主役”となったのが、平賀譲だ。東京帝大造船学科を卒業して海軍に入り、造船技術者として活躍し、途中から東京帝大教授を兼任していた。蓑田らが攻撃した河合の著書が発禁処分となり、前任総長が病弱で心労を重ねたことから、後任に指名された。異例の軍人総長だった。
当時、経済学部教授陣は、自由主義の河合派に対し、国家主義を掲げる土方成美派の抗争が続いていた。平賀はこの内紛を解決するため、けんか両成敗で2人を休職処分とした。
だが経済学部教授会に諮らず、文部省に上申して処分を決めたため、教授会は大揺れとなり、両派や法学部の教授ら13人が辞表を提出した。一部は撤回したが、結果的に13人全員が追放されることになった。
この「平賀粛学」以降、吉野や美濃部らに代表された東京帝大内のリベラルな学者らは姿を消した。
必ずしも好戦的ではなかった
平賀総長の意外な一面
平賀は必ずしも好戦的な人物ではなく、陸軍には好意的な態度を取らなかった。東條英機首相の卒業式出席には最後まで反対した。
それでも戦時中の演説は好戦的だった。真珠湾を攻撃した直後の41年12月27日に挙行された繰り上げ卒業式では、「戦が長期戦となることは覚悟の上であります。我らは必勝の信念を堅持し、あくまでこの乾坤一擲の大戦争に勝ち抜いて大東亜新秩序建設し、もって世界の平和に寄与せねばなりません」と卒業生を鼓舞している。