
長谷川智
“日本フットボールの父”が母校を訪れて言葉を失った、立教大「キリスト教大弾圧」の爪痕
終戦後間もなく、GHQ係官だったポール・ラッシュは、かつて自身が教授通して教鞭をとっていた東京・池袋の立教大学を訪れて、その荒廃ぶりに深く落胆した。立教大学は戦時中、軍部や文部省の圧力で「キリスト教主義教育」の看板を下ろし、「皇国の道」による教育を強いられた。その契機となった「チャペル事件」を踏まえ、立教大が「学問の自由」を取り戻すまでの道のりを振り返ってみよう。

法政大と明治大の権力闘争を言論封殺に利用した、右翼・軍部の「巧妙な手口」
自由な校風で知られる、法政大と明治大。創設時期も近く共通点が多い両校だが、学内の騒動などを機に軍人や警察官僚が招き入れられ、戦時色に染まっていった経緯も似ている。とりわけ「法政騒動」は右翼の大物が学内の実権を握る契機となった。戦時下で進められた私学の言論封殺を、具に検証しよう。

日本の主権者は天皇か、国民か?東大に国粋主義と民本主義が同居する宿命、そこで教えられていたこと
戦前に国粋主義者、蓑田胸喜が主導して糾弾した滝川事件や天皇機関説事件は、東京六大学や社会から自由な言論が消える契機となった。蓑田という人物を生み、その跳梁跋扈を許すことになった土壌や背景には、東京帝大の持つ「宿命的二重性」がある。国粋主義と民本主義が同居する東大では、当時どんな授業が行われていたのか。

立花隆が「異常な男」と批評、戦前に数知れない知識人を葬り去った「言論弾圧の怪物」とは
戦前の言論弾圧として有名な滝川事件と天皇機関説事件の2つについて、影の仕掛け人と呼ばれる男がいる。国粋主義者の蓑田胸喜だ。そのやり方は、自由な言論を展開する識者に対してレッテル貼りなどによる執拗な攻撃を行ったり、国体に議会や官僚、軍部まで巻き込んで圧力をかけたりするものだった。後年、ジャーナリストの立花隆が「異常な男」と呼んだ蓑田の素顔とは。
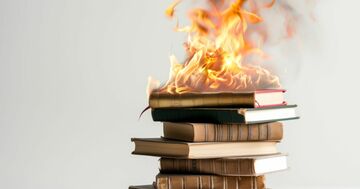
戦争は突然起こるわけではない、戦前の六大学を巻き込んだ「文化戦争」の3つの時期
野球で有名な六大学だが、戦前は学の独立を脅かされる「文化戦争」に巻き込まれた時期もあった。政府・軍と東京六大学の関係は、時期と大学によって異なるが、大学が設立された19世紀後半から1945年の敗戦に至るまで、3つの時期に分けることができる。そこでは、どんな言論封殺が起きていたのか。

上皇を教育したリベラリスト・小泉信三が、戦中の慶大塾長時代に「好戦家」へと豹変した“止むに止まれぬ事情”
戦時中に慶應義塾大学塾長を務めた小泉信三は、自由主義経済学者、マルクス主義批判の知識人として知られ、戦後は皇太子教育の全権委任者を務めたリベラリストとして知られる。しかし塾長時代はあたかも学生を戦地に送り出すことに情熱を注いでいるのではと思われるほど好戦的な言論を展開した。全く異なる小泉の「2つの顔」の裏には、何が隠されていたのか。

学の独立か、大学の存続か…戦時下の大弾圧を乗り切った早大総長の評価が今も分かれる理由
1943年に学徒出陣を控えた早稲田大学と慶應義塾大学の野球部の壮行試合、いわゆる「最後の早慶戦」が行われた裏で、試合の実現に向けた土壇場の駆け引きがあったことをお伝えした。開催に最後まで難色を示したのは、早稲田の田中穂積総長だった。折しも当時の早稲田は、数々の言論弾圧に見舞われていた。軍部に睨まれた早稲田を存続させるために難しい舵取りを迫られた田中総長は、どのような選択を迫られていたのだろうか。

「最後の早慶戦」はなぜ実現したのか?軍部に睨まれた早稲田大学で起きていた土壇場の駆け引き【東京六大学野球連盟発足100年】
1925年に東京六大学野球連盟が発足して、今年で100年。当時は六大学に言論封殺の影が漂い始めた頃だ。世界各地で戦争が勃発し、学問の場で言論封殺が起きている現代に通じる雰囲気がある。再び世界や日本が誤った方向に進まないためにも、当時の世相を改めて検証することは重要だ。戦前・戦中の時代を、東京六大学はどう「学問の自由」を守り抜いてきたのだろうか。軍部に睨まれていた早稲田大学で行われた、「最後の早慶戦」をめぐる土壇場の駆け引きとは。
