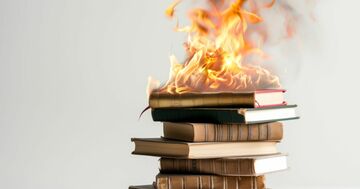立教大学は米国聖公会によって設立された。創立者は、チャニング・ムーア・ウィリアムズという米国ヴァージニア州生まれの米国聖公会の牧師だ。清国で伝道活動に従事した後、1859年に長崎に来て、高杉晋作や大隈重信らと交流した。その後、東京に移り、74年に立教大学の起源となる私塾「立教学校」を築地に開設。1907年に立教大学として認可され、18年に池袋に移転し、現在に至っている。
25年に新設された学長には米国人宣教師、チャールズ・シュライバー・ライフスナイダーが就任した。日本の大学で初めての外国人総長となるなど、日米開戦時まで米国人が理事長など要職を務め、大学経営の主導権を握っていた。
キリスト教系学校に対する本格的な排撃は、満州事変の翌年にあたる1932年に起きた上智大学生の靖国神社参拝拒否事件とされる。学校教練のため配属されていた陸軍将校が、上智大生を引率して靖国神社を参拝したが、カトリック信者の一部の学生が本殿に参拝しなかった。軍部は問題視し、配属将校を引き揚げる意向を示した。
当時、配属将校を受け入れて教練を履修すると兵役が短縮されたため、大学にとっては学生集めで有利だった。事件が報道されて非難が高まると、設置母体であるカトリック協会は事態収拾のため、参拝を全面的に受け入れた。
立教の命運を決めた「チャペル事件」
祭壇下での教育勅語奉読が「不敬」に
立教の「チャペル事件」も、こうして戦時色が強まるなかで起きた。天皇誕生日である4月29日の天長節祝賀式で、学長の木村重治が祭壇の下で教育勅語を奉読したが、これが不敬であると問題視されたのだ。
例年は教室で行っていた祝賀式をチャペルで開き、祭壇や説教台より一段低い場所で勅語を奉読したことを批判された。木村は7月、辞任に追い込まれ、大学当局はその後、御真影と教育勅語謄本の受け入れを政府に申請した。戦時体制に向かう大きな一歩となった。
満州事変をきっかけに緊張が高まっていた日米関係は、年々悪化していく。米国聖公会との関係も危うくなり、外国人教師の帰国が相次いだ。1940年にはライフスナイダーが理事長と総長を辞任、日本人が後任を引き継いで「日本化」が深まっていく。