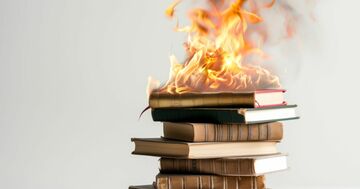チャペル事件の伏線には、文学部長兼立教中学校長を木村によって解職された小島茂雄と木村との確執があったという。2人とも立教の卒業生だが、小島は聖職者で立教勤務が長く、米聖公会との関係も良好だった。一方、木村は長崎高等商業学校の校長を務めるなど官立学校勤務が長く、非主流派に招かれて立教大学の教壇に立ち、学長に就任した経緯があった。
木村が小島を解職した理由は、小島の博士学位に詐称の疑いがあったとされているが、これに対して小島側が「チャペルでの木村の行動は不敬だ」と反撃して対抗した。不敬だという非難は当時、大学に配属されていた将校から出たとされているが、小島がそこにつけ込んで増幅し、最終的に木村を辞任に追い込んだ。
派閥争いがなければ、不敬事件はどうなっていたのだろうか。権力は攻撃する対象の分断を歓迎する。文化戦争を考える問題提起になる。
学内の暴力事件がきっかけで
寄付行為の名目もターゲットに
42年に、寄附行為に明記していた「キリスト教主義の教育」を削除したのも、発端となったのは、直前に発覚した学生暴行事件だった。ボクシング部の部員が、普段からキリスト教排撃論を唱えていた射撃部副部長の予科教授らに暴行したが、この事件の直後から大学は、寄附行為の変更に動いた。
当時の大学配属将校は「狂的愛国主義者」と評され、大学当局や学生らを強い姿勢で抑えていた。こうした空気の中、学内の会議で経済学部長らが「キリスト教主義の文字を抹殺すべきだ」と主張。立教中学教諭らもそれぞれ個別に学長に対してキリスト教排撃を脅迫的言辞で迫っていた。配属将校の強硬姿勢が、学内関係者のキリスト教排撃と分断を生んでいたようだ。
ただ、軍の配属将校は「暴行事件は学内で処理すべきで、軍に持ち込む意思はない」としており、寄附行為の変更を求めた事実は確認されていない。大学内部から生まれた軍への同調や忖度が、分断に拍車をかけたと考えられる。