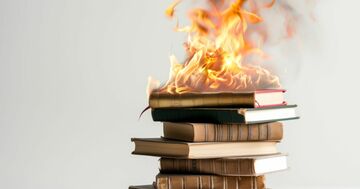文部省で大学監督を担当していた課長が「大学内の対立は例外なしに内部のあつれきですよ」と述べていた証言もある。
『立教学院史研究』の論文は、寄付行為の変更の過程で、「軍や文部省などからの直接の圧力は確認できず、むしろ当時の学内状況が大きく作用した可能性が資料から示唆される。政府による統制が強まった戦時中は、学校内部からの内在的問題の展開を踏まえなければ、説明できないことも少なくないだろう」と権力からの圧力で生まれる内部対立の影響の大きさを書いている。
時局の変化によって学内に亀裂が生まれ、自らが意識的に時代に迎合した部分も少なくないという。異論を抑えるため、権力が本気で異論封殺を仕掛けてくる「文化戦争」に大学は抗しがたい。文化戦争の強大な圧力の中で、大学内にも同調する動きが生まれ、分断が進むのだ。
「文化戦争」への貴重な示唆
連携し、異論封殺の萌芽を摘むことが重要
ただ一方で、大学全体が時代に迎合したわけでもなかった。英米文学研究の先駆者とされた文学部教授の富田彬は当時から、戦争への迎合の風潮を公然と批判した論文を書いている。
富田は戦後にヴァージニア・ウルフの『ダロウェイ夫人』やハーマン・メルヴィルの『白鯨』を翻訳した人物だが、戦時中に次のような文章を記している。(注1)
「文学をやるものは文学以外のことをあまり考えないでいいのである。文学をやる者が政治のことや金儲けのことなどを考えるのは邪道である。政治が気になり金儲けがしたくなったら、文学をやめてそういう方向へ向かって行けばいいと思う」(42年8月『文学の研究』、原載不明)。
「文学は、直接に何かの役に立とうとする時に堕落し始める。そういう文学は、文学でないが故に、何の役にも立たないのである」(43年6月『文学と数寄』、同)