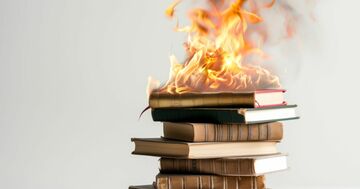キリスト教主義の教育を放棄
「皇道教育」を掲げて「日本化」する立教
当局の統制が強まり、キリスト教系学校は、運営する財団法人の基本ルールである「寄附行為」に明記していた教育理念について、相次いで表現の変更を余儀なくされた。プロテスタント系は、キリスト教主義の教育を標榜すると明記していたが、明治学院や同志社、青山学院などは、「教育勅語を尊重し」という趣旨の文言を付け足した。
大学のほか中学や高校なども運営する財団法人だった立教学院は41年、理事の選出規定を米国聖公会から日本聖公会中心に改め、翌年9月には根本的な変更を加えた。第二条の「キリスト教主義による教育」を削除し、「皇国の道による教育」に改めたのだ。教育勅語を尊重する趣旨を加えた学校は多いが、キリスト教主義を放棄した例はほとんどなかった。
「皇国の道」という表現を採用した法人もなく、キリスト教色を徹底的に排除したという意味では、極めて特異な変更だった。10月にはチャペルを閉鎖し、「修養堂」と改称した。校歌「栄光の立教」の一節にある「自由の学府」が問題視されたため、校歌斉唱を禁止した。
教授らへの弾圧も起き、42年には、経済学部教授の宮川実が、治安維持法違反で検挙され、辞職に追い込まれた。宮川は東京帝大法学部を卒業し、京都帝大の河上肇門下となり、マルクス主義経済学を研究。和歌山高等商業学校などに赴任した後、立教大学で教えていた。
検挙の理由は、前年に東北帝大で検挙された左翼学生が、宮川の和歌山時代の教え子で、影響を与えている疑いがあるということだった。
(改ページ)
この頃、米国聖公会によって設立された築地の聖路加国際病院と協力し、医学部を設置する構想が具体化していた。しかし、戦争遂行のため理工系重視の教育方針が打ち出されたため、医学部構想は頓挫。文学部を廃止し、理科専門学校(後の理学部)が設立された。
こうした「日本化」「戦時体制」が解除されたのは、戦後、ラッシュが戻ってきてからだ。ラッシュは立教にキリスト教に基づく学校再建を指示。寄附行為を「キリスト教による教育を行う」に改め、文学部も復活させた。その後に多くの学部を新設されて総合大学となった。
新たに判明した弾圧の虚実
内紛がらみで自ら統制を受け入れ?
戦時体制下の立教のこうした歴史は、キリスト教系大学に対する文部省・軍部による統制の強化が背景にあることは間違いない。しかし近年、他の一面も判明しつつある。
異論排除をめぐる文化戦争の新しい一面を知ることができる。きっかけは、2000年に設立された立教学院史資料センターの設立だ。「立教学院百二十五周年史」の編さん作業を終了した後、2024年度の「百五十周年史」編さんに向けて資料を集め始めたが、研究を進めると新しいことがわかってきた。
戦争遂行に向けて、政府と軍部が大学への統制を強め、異論を封殺していった大状況は変わらない。しかし、具体的状況を調べていくと、さまざま圧力を受けて、大学内に力関係の変化が生まれ、従来からの派閥やグループ間の抗争がからんで、大学自らが統制を受け入れてきた側面が見えてきた。
同センターが年に1回発行している『立教学院史研究』から探ってみたい。たとえば、チャペル事件は、学長の木村重治による祭壇での教育勅語の奉読が不敬とされたが、後に学長に就任した遠山郁三の日誌を翻刻した解説では、「学内の派閥争いの側面も持っていたともみられる」と記述されている。